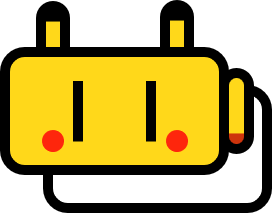静電気学における仕事とエネルギー
電荷を動かすためにした仕事1
$$ -\int_\mathbf{a} ^\mathbf{b} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_\mathbf{a} ^ \mathbf{b} \left( \nabla V \right) \cdot d\mathbf{l} = V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) $$
したがって、固定された源電荷分布があり、テスト電荷 $Q$を点 $\mathbf{a}$から点 $\mathbf{b}$まで動かすときの仕事は次のように計算されます。
$$ W=\int_{\mathbf{a}}^\mathbf{b} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = -Q\int_\mathbf{a}^\mathbf{b} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} =Q[V(\mathbf{b})-V(\mathbf{a})] $$
この式を $Q$で割ると以下のようです。これは、$\mathbf{a}$と$\mathbf{b}$の電位差は電荷 $Q$を$\mathbf{a}$から$\mathbf{b}$へ動かすのに必要な仕事と同じという意味です。
$$ V(\mathbf{b})-V(\mathbf{a})=\dfrac{W}{Q} $$
とても遠い場所から位置 $\mathbf{r}$へ電荷 $Q$を動かすときの仕事は,
$$ W=Q[V(\mathbf{r}) - V( \infty ) ]=QV(\mathbf{r}) $$
点電荷分布のエネルギー
空っぽの空間からとても遠い場所にあった電荷 $q_{1}$を動かしてきたとしましょう。空間が空だったので、電場はなく、したがって仕事も発生しません。
次に、電荷 $q_2$を遠い場所から $\mathbf{r}_2$へ動かしてくるとします。今、$q_{1}$があるため、電場があり、$q_2$を動かすための仕事が発生します。$q_{1}$が作る $\mathbf{r}_2$での電位を$V_{1}(\mathbf{r}_2)$、$q_2$を動かした後の$q_{1}$との距離を$\cR_{12}$としましょう。すると、上で導出した式によって、
$$ W_2=q_2V_{1}(\mathbf{r}_2)=q_2\dfrac{1}{4\pi\epsilon_{0}}\dfrac{q_{1}}{\cR_{12}} $$
同様に、電荷 $q_{3}$を遠い場所から$\mathbf{r}_{3}$へ動かすとします。$q_{1}, q_2$が作る電場の影響を受けるため、
$$ W_{3}=q_{3}\left[ V_{1}(\mathbf{r}_{3})+V_{2}(\mathbf{r}_{3}) \right] =q_{3}\dfrac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \left( \dfrac{q_{1}}{\cR_{13}}+\dfrac{q_2}{\cR_{23} }\right) $$
同様に、電荷 $q_{4}$を持ってくると、
$$ W_{4}=q_{4}\left[ V_{1}(\mathbf{r}_{4}) +V_2(\mathbf{r}_{4}) +V_{3}(\mathbf{4}) \right]=q_{4}\dfrac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \left( \dfrac{q_{1}}{\cR_{14}}+\dfrac{q_2}{\cR_{24}} +\dfrac{q_{3}}{\cR_{34}}\right) $$
したがって、最初の4つの電荷を集めるのに必要な仕事の合計量は、
$$ W=\dfrac{1}{4\pi\epsilon_{0}}\left(\dfrac{q_{1}q_2}{\cR_{12}} +\dfrac{q_{1}q_{3}}{\cR_{13}}+\dfrac{q_{1}q_{4}}{\cR_{14}}+\dfrac{q_2q_{3}}{\cR_{23}}+\dfrac{q_2q_{4}}{\cR_{24}}+\dfrac{q_{3}q_{4}}{\cR_{34}} \right) $$
$n$個の電荷を動かすことに一般化すると、
$$ W=\dfrac{1}{2}\dfrac{1}{4\pi\epsilon_{0}}\sum \limits_{i}^n \sum \limits_{j \ne i } ^n \dfrac{q_{i}q_{j}}{\cR_{ij}} $$
$i=2$、$j=3$の場合と$i=3$、$j=2$の場合は同じなので、全体の場合数から$2$を割りました。要約すると、
$$ W=\dfrac{1}{2}\sum \limits_{i}^n q_{i} \left( \sum \limits_{j \ne i} ^n \dfrac{1}{4 \pi \epsilon_{0}}\dfrac{q_{j}}{\cR_{ij}} \right) $$
この時、括弧内は $q_{i}$が存在する場所$\mathbf{r}_{i}$が存在する場所に$j\ne i$の$q_{j}$たちが作る電位ですので、
$$ W=\dfrac{1}{2}\sum \limits_{i}^n q_{i}V(\mathbf{r}_{i}) $$
これは、集まっている点電荷たちに蓄えられたエネルギーを意味します。
連続した電荷分布のエネルギー
点電荷について導出した式を線電荷密度、面電荷密度、体積電荷密度についてそれぞれ表すと、
$$ \begin{align*} W &= \frac{1}{2} \int \lambda V dl \\[1em] &= \frac{1}{2} \int \sigma V da \\[1em] &= \frac{1}{2} \int \rho V d\tau \end{align*} $$
体積電荷に対する式で、ガウスの法則 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \dfrac{\rho}{\epsilon_{0}}$を使って $\rho$の代わりに $\mathbf{E}$で表すと、
$$ W=\dfrac{\epsilon_{0}}{2} \int (\nabla \cdot \mathbf{E}) V d\tau $$
この式は部分積分法を使って以下のように変形できます。
$$ W=\dfrac{\epsilon_{0}}{2} \left[ -\int \mathbf{E} \cdot (\nabla V)d\tau + \oint V\mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \right] $$
$\nabla V=-\mathbf{E}$なので、
$$ W= \dfrac{\epsilon_{0}}{2} \left[ \int _\mathcal{V} E^2 d\tau + \oint_\mathcal{S}V\mathbf{E}\cdot d\mathbf{a} \right] $$
この場合、積分領域は電荷を含む領域であればどのような領域でも構いません。電荷がない場所の電荷密度は$\rho=0$なので、全ての電荷を含む限り、積分領域をいくらでも大きくしても結果は変わりません。最初の項を見ると、積分領域が広がると積分値は積分関数が正であるため、続けて大きくなります。全体の値は$W$で固定されているので、最初の項の大きさが大きくなるほど、二番目の項である面積分の値は続けて小さくなります。したがって、全体の空間に対して積分すると、
$$ W=\dfrac{\epsilon_{0}}{2} \int_{\mathrm{total\ space}} E^2 d\tau $$
David J. Griffiths, 電磁気学入門(Introduction to Electrodynamics, 金田 進訳) (第4版, 2014), p100-106 ↩︎