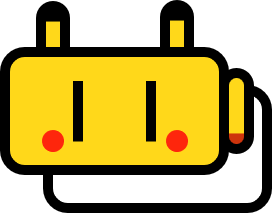電気フラックスとガウスの法則
定義1
面 $\mathcal S$を通過する電場 $\mathbf{E}$のフラックスを以下のように定義する。
$$ \Phi_{E} \equiv \int_{\mathcal S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} $$
これから、$\mathcal{S}$をある閉じた曲面としよう。閉じた曲面内の総電荷量を$Q_{\text{in}}$としよう。すると、次の式が成り立つ。
$$ \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_{0}}Q_{\mathrm{in}} $$
これをガウスの法則という。
フラックス
フラックスとは、ある物理量が特定の面に対して垂直に通過する量をいう。例えば、管を流れる水やガスは、その管の垂直面に対して平行に流れるため、流れる量自体がフラックスと同じである。しかし、電場は管に沿って流れない。そのため、電場のフラックスは内積を使って求める。内積を取ると、平行でない成分はすべて0として計算されるからである。

ある面を通過する電場線が上の図のようだとしよう。ここで私たちが知りたいのは、面に垂直に通過する程度がどれくらいかということだ。みんな知っての通り、ベクトルは分解が可能だ。電場線を面に垂直な方向と平行な方向に分解しよう。すると下の図のようになる。  私たちの目的は、図で示された$\mathbf{E}_\parallel$を求めることである。面ベクトル$d\mathrm{a}$の大きさは$1$であるため、内積を使って以下のような式で求めることができる。
私たちの目的は、図で示された$\mathbf{E}_\parallel$を求めることである。面ベクトル$d\mathrm{a}$の大きさは$1$であるため、内積を使って以下のような式で求めることができる。
$$ \mathbf{E}_\parallel=\mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} $$
上で行った方法に従って、与えられた面に対する電場のフラックスを以下のように定義する。
$$ \Phi_{E} \equiv \int_{\mathcal S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} $$
ガウスの法則(積分形)
ガウスの法則の核心は、閉じた曲面の外にある電荷はフラックスに何の影響も与えないということである。

図を見れば、閉じた曲面を外から貫通する電場線によるフラックスは、面の両端で2回計算されることがわかる。閉じた曲面における面ベクトルの方向は常に面の外側に定義される。両端の面ベクトル方向が正反対であるため、両端を通過するフラックスの大きさは同じで、方向は違う。この2つを加えると$0$になるため、閉じた曲面の外の電荷はフラックスに影響を与えない。
導出
これから、点電荷$Q$が半径$r$の球の中心にあるとしよう。このとき、球面を通過する電場$\mathbf{E}$のフラックスを求めてみよう。クーロンの法則で電場を表すと、次のようになる。
$$ \begin{align*} \Phi_{E} &= \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \\ &= \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^\pi \left( \frac{Q}{4\pi\epsilon_{0} r^{2}} \hat{\mathbf{r}} \right) \cdot \left( r^{2}\sin\theta d\theta d \phi \hat{\mathbf{r}} \right) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}}Q \int_{0}^{2\pi}d\phi \int_{0}^\pi \sin\theta d\theta \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}}Q (2\pi)(2) \\ &= \frac{1}{\epsilon_{0}}Q \end{align*} $$
結果を見ると、半径$r$に対して無関係であることがわかる。これは球の表面積が$r^{2}$に比例し、電場が$r^{2}$に反比例するからである。お互いに打ち消しあって、結果に影響を与えない。曲面内に複数の点電荷がある場合は、単純に加えればよい。複数の点電荷による電場が重ね合わせの原理に従って単純に加えられるからである。例えば、点電荷$Q_{1}$、$Q_{2}$があり、$Q=Q_{1}+Q_{2}$とすると、結果は下のようになる。
$$ \begin{align*} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} &= \oint \left( \sum \limits_{i=1}^{2} \mathbf{E}_{i} \right) \cdot d\mathbf{a} \\ &= \oint \left( \mathbf{E}_{1} + \mathbf{E}_{2} \right) \cdot d\mathbf{a} \\ &= \oint \mathbf{E}_{1} \cdot d\mathbf{a} + \oint \mathbf{E}_{2} \cdot d\mathbf{a} \\ &= \frac{1}{\epsilon_{0}}Q_{1}+\frac{1}{\epsilon_{0}}Q_{2} \\ &= \frac{1}{\epsilon_{0}}(Q_{1}+Q_{2})=\frac{1}{\epsilon_{0}}Q \end{align*} $$
当然、点電荷が3つ以上の場合も結果は同じである。したがって、閉じた曲面内の総電荷量を$Q_{\text{in}}$とし、各電荷が作る電場の合計である総電場を$\mathbf{E}$とすると、次の式が成り立つ。
$$ \begin{equation} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \dfrac{1}{\epsilon_{0}}Q_{\text{in}} \label{1} \end{equation} $$
微分形
$$ \int_\mathcal{V} \nabla \cdot \mathbf{v} d\tau = \oint _{S} \mathbf{v} \cdot d \mathbf{a} $$
$\eqref{1}$に発散定理を適用すると、以下の式を得る。
$$ \int_{\mathcal{V}} \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau = \oint _{\mathcal{S}} \mathbf{E} \cdot d \mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_{0}}Q_{\text{in}} $$
このとき、単位体積当たりの電荷量を体積電荷密度$\rho$としよう。すると、体積内部の総電荷量$Q_\mathrm{in}$と$\rho$の関係は以下のようになる。
$$ Q_\mathrm{in}=\int_\mathcal{V} \rho d\tau $$
上の2つの式の結果を組み合わせると、以下のようになる。
$$ \begin{align*} && \int_\mathcal{V} \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau &= \int_\mathcal{V} \frac{1}{\epsilon_{0}}\rho d\tau \\ \implies && \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{1}{\epsilon_{0}}\rho \end{align*} $$
これをガウスの法則の微分形といい、マクスウェル方程式のひとつである。
David J. Griffiths, 基礎電磁気学(Introduction to Electrodynamics, 金晋昇訳)(4th Edition). 2014, p73-77 ↩︎