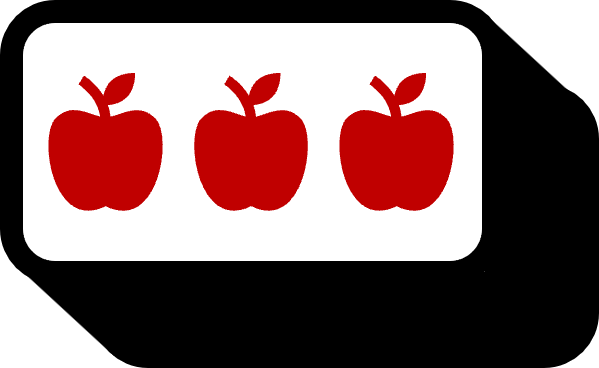強制調和振動と共鳴振動数
強制調和振動1
物体がバネに吊るされ振動するような運動を調和運動と言う。このとき、空気抵抗などの摩擦力を含む他の外力が存在せず、バネ定数$k$による復元力だけが働いている場合を単純調和振動と呼ぶ。摩擦力のように速度に比例する外力が存在する場合は減衰調和振動と呼ばれる。ここに外部から周期的な力、駆動力駆動力が系に作用する場合を強制調和振動強制調和振動と言い、運動方程式は以下の通りである。
$$ \begin{equation} m\ddot{x}= -kx -c\dot{x} +F_{0}\cos \omega t \end{equation} $$
- $-c\dot{x}$ : 減衰項、速度に比例する外力(摩擦力など)
- $F_{0}\cos \omega t$ : 周期的な外力
強制振動システムでは、共鳴共鳴という特異な現象が起こる。駆動力の振幅$F_{0}$と無関係に、固定されていてさえも、駆動力の振動数、すなわち駆動振動数$\omega$が系の固有振動数$\omega_{0}$に近いとき、振幅が大きくなることをいう。これを簡単に理解する良い例がブランコである。一人でブランコに乗るとき、1秒間に行ったり来たりした回数が系の固有振動数である。もし後ろから押してくれる人がいれば、その押してくれる力が駆動力となり、1秒間に押してくれる回数が駆動振動数になるだろう。経験的によく知っているように、ブランコが最も後ろに行って前に出るときに押すと、一番遠くに出る。これを力学的に説明すると、「駆動振動数が固有振動数に近いほど、振幅が大きくなる現象、すなわち共鳴現象が起こる」となる。それでは、強制調和振動で減衰がある場合とない場合に分けて見てみよう。
減衰がない場合
減衰項がなければ$(1)$は以下のようになる。
$$ \begin{equation} m\ddot{x} +kx =F_{0}\cos \omega t \label{eq2} \end{equation} $$
この微分方程式の解は$\cos$で示される。または「ある関数を2回微分したものとその関数を足してコサインが出るようにするには、その関数がコサインでなければいけない」と単純に考えても良い。だから、解を以下のようにしよう。
$$ x(t)=A \cos (\omega t -\phi) $$
これを$(2)$に代入すると次のようになる。
$$ \begin{align*} &&- m\omega^{2}A \cos (\omega t -\phi)+kA\cos (\omega t - \phi)&=F_{0}\cos \omega t \\ \implies && (k- m\omega^{2})A \cos (\omega t -\phi)&=F_{0}\cos \omega t \end{align*} $$
この式が成立するには$\phi=0$、$\phi=\pi$でなければならない。平行移動してコサイン関数の関数値の符号を変えることを含めて、同じ形が出る場合はこれら2つの場合しかないからである。すると、振幅$A$は次のようになる。
$$ A= \begin{cases} \dfrac{F_{0}/m}{{\omega_{0}}^{2}-\omega^{2}} & \phi=0,&\omega < \omega_{0} \\[1em] \dfrac{F_{0}/m}{\omega^{2}-{\omega_{0}}^{2}} & \phi=\pi,&\omega > \omega_{0} \end{cases} $$
この時$\omega_{0}=\sqrt{k/m}$は系の固有振動数である。$\omega_{0}=4$、$F_{0}/m = 1$として駆動振動数による振幅のグラフを描くと以下のようになる。

減衰がある場合
速度、すなわち、一度微分された項が式に含まれているため、駆動力を指数関数として表現するのが良い。振幅が$F_{0}$、振動数が$\omega$の振動を指数関数として表現すると$F_{0}e^{i\omega t}$となるので$1$は以下の通りである。
$$ \begin{equation} m\ddot{x}+c\dot{x}+kx = F_{0}e^{i\omega t} \label{eq3} \end{equation} $$
それでは、減衰がない場合と同様に、解を以下のようにしよう。
$$ x(t)=A e^{i(\omega t-\phi)} $$
これを$\eqref{eq3}$に代入すると、以下の式が得られる。
$$ -m\omega ^{2}Ae^{i(\omega t -\phi)}+i\omega cAe^{i(\omega t -\phi)}+kAe^{i(\omega t - \phi)}=F_{0}e^{i \omega t} $$
両辺に$e^{-i (\omega t -\phi)}$を掛けると次のようになる。
$$ -m\omega ^{2}A+i\omega cA+kA=F_{0}e^{i \phi}=F_{0}(\cos \phi +i \sin \phi) $$
右辺はオイラーの公式によって成立する。この式を実部と虚部に分けると次のようになる。
$$ \begin{equation} \begin{aligned} A(k-m\omega^{2}) = F_{0}\cos \phi \\ c\omega A = F_{0} \sin \phi \end{aligned} \label{eq4} \end{equation} $$
下の式を上の式に割ると、位相差$\phi$に関する条件が得られる。
$$ \frac{c\omega}{k-m\omega ^{2}}=\tan \phi $$
さらに$\eqref{eq4}$から$\sin ^{2} \phi + \cos ^{2} \phi=1$であることを利用すると、以下の式が得られる。
$$ A^{2}(k-m \omega ^{2})^{2} + c^{2} \omega^{2} A^{2} =F_{0}^{2} $$ 振幅について整理すると次のようになる。
$$ \begin{align*} A(\omega) &= \frac{F_{0}}{\sqrt{(k-m \omega ^{2})^{2} + c^{2} \omega^{2}}} \\ &= \frac{F_{0}/m}{\sqrt{(k/m- \omega ^{2})^{2} + c^{2} \omega^{2}/m^{2}}} \\ &= \frac{F_{0}/m}{\sqrt{({\omega_{0}}^{2}- \omega ^{2})^{2} + 4\gamma ^{2}\omega^{2}}} \end{align*} $$
この時$\omega _{0}$は系の固有振動数、$\gamma=\frac{c}{2m}$は減衰係数である。さて、共鳴が起こる振動数を求めよう。分母が$0$の時$A(\omega)$が発散するので、以下のようにしよう。
$$ ({\omega_{0}}^{2}-\omega^{2})^{2}+4\gamma ^{2} \omega^{2} = 0 $$
$0$は微分しても$0$なので、上の式を$\omega$に対して微分すると次のようになる。
$$ 2({\omega_{0}}^{2}-\omega^{2})(-2\omega) + 8\gamma^{2}\omega=0 $$
$\omega$に対して整理すると以下のようになる。
$$ {\omega_{r}}^{2}=\omega^{2}={\omega_{0}}^{2}-2\gamma^{2} $$
$\omega$が上記のような時$A(\omega)$が発散する共鳴が起こるので、この振動数を共鳴振動数と呼び$\omega_{r}$と表記する。$r$は共鳴から導かれている。減衰係数$\gamma$が小さいほど、共鳴振動数は固有振動数$\omega_{0}$に近くなることがわかる。$\omega_{0} = 2$の時、$\gamma$の値による振幅のグラフは以下のようになる。$\gamma$が小さくなるほど、グラフのピークが$2$に近くなることが見られる。

参照
Grant R. Fowles and George L. Cassiday, Analytical Mechanics (第7版, 2005), p113-118 ↩︎