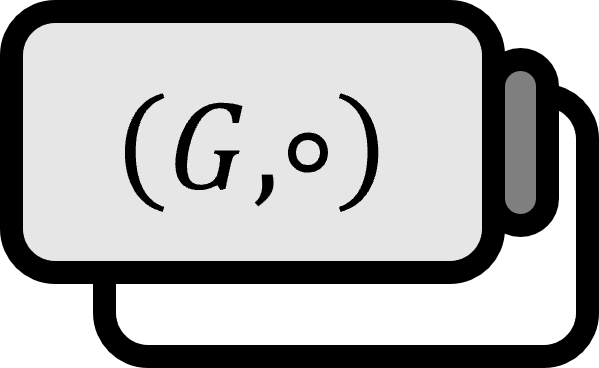抽象代数における二項演算
ビルドアップ
数学を大きく三つに分けるなら、幾何学、解析学、代数学と言えるだろう。その中で、代数学は教育課程で学ぶ二項、約分などを扱う数学の一分野だった。代数学とは基本的に「数」の代わりに文字を使ってどんな方程式でも解くことを目標とする学問だ。特定の数に限らず、一般的で強力な解法を探求するため、当時は最先端技術と言えた。しかし、このような数学的テクニックは教育が発達した現代では誰にでも当たり前の常識のようになった。
一方、数学界はこれらの概念をさらに発展させ、「数」を超えて抽象的な「構造」に関心を持ち始めた。我々がもともと「数」と「計算」と呼んでいたものを「元素」と「演算」に抽象化したのだ。だから、現代代数学は代数的テクニックを使える条件やあるいは構造自体を研究する学問になった。上の説明から想像できるように、現代代数学は特に抽象的な面が強く、一般に「抽象代数学」と呼ばれる。
抽象代数学で関心を持つのは主にある集合とその集合で定義される演算の性質だ。集合$S$と演算$\ast$が与えられているなら、$S$は$\ast$に対して閉じているか、単位元は存在するか、逆元は存在するかなどを研究する。その中でも抽象代数学で関心を持つ演算は、$a \ast\ b = c$のように二つの元が一つの元に対応する二項演算二項演算だ。
定義1
- 二項演算は$\ast : S \times S \to S$で定義される関数と見なせ、そのような二項演算が定義される集合を二項演算構造と言う。
- 集合$M \ne \emptyset$の元素$a,b$と二項演算$\ast$に対して、$a * b \in M$ならば$\left< M , \ast\ \right>$をマグママグマと定義する。
説明
マグマは抽象代数学が関心を持つ二項演算構造の中でも最も単純な概念だ。単に閉じている閉じているだけで良い。
マグマになれない例
奇数の集合を$O$、無理数の集合を$I$としたら、$\left< O , + \right>$と$\left< I , \cdot \right>$はマグマではない。
マグマになれない例としては、奇数の集合や無理数の集合などがある。これらは乗算や加算などに対して閉じていないため、二項演算構造であってもマグマになれない。
- 奇数の集合を$O$とした時、加算を考えると二つの奇数の和は必ず偶数なので$O$は閉じておらず、マグマになれない。
- 無理数の集合を$I$とした時、$I$で乗算を考えると$\sqrt{2} , 2\sqrt{2} \in I$であり$\sqrt{2} \cdot 2 \sqrt{2 } = 4 $だが、$ 4 \notin I$なので$I$はマグマではない。
マグマになる例
任意の集合$S$のべき集合$\mathscr{P}(S)$と差集合$\setminus$について$\left< \mathscr{P}(S) , \setminus \right>$はマグマだ。
- $S$の部分集合$A$と$B$について、$( A \setminus B ) \subset S$なので、$( A \setminus B ) \in \mathscr{P}(S)$であり$\left< \mathscr{P}(S) , \setminus \right>$はマグマだ。
演算も重要だ
大切なことは、代数的構造を探求する時は集合そのものだけでなく、演算も一緒に考えなければならない点だ。マグマにならない例をもう一度見よう。
奇数の集合を$O$、無理数の集合を$I$としたら、$\left< O , \cdot \right>$はマグマだが、$\left< I , + \right>$はマグマではない。
- 奇数の集合を$O$とした時、乗算を考えると二つの奇数の乗算は必ず奇数なので、$O$は閉じておりマグマになる。
- 無理数の集合を$I$とした時、$I$で加算を考えると$\sqrt{2} , -\sqrt{2} \in I$であり$\sqrt{2} + ( - \sqrt{2 } ) = 0$だが、$ 0 \notin I$なので$I$はマグマではない。
奇数の集合は演算を変えることでマグマになったが、無理数の集合は依然としてマグマになれなかった。つまり、今は意味がないと思われる集合も、与えられた演算によっては意味のある代数的構造を持つ可能性があるということだ。
一方で、マグマの定義は非常にシンプルで一般的なため、マグマ自体が有用な性質を提供するわけではない。マグマという名前自体が我々が知る「溶岩」に同じルーツを持ち、フランス語で「ごちゃごちゃしたもの」という意味を持つ。それだけ多くの代数的構造がマグマから始まるが、その概念自体はそれほど重要ではないと言えるだろう。
Fraleigh. (2003). アブストラクトアルジェブラ序論(第7版): p20, 29. ↩︎