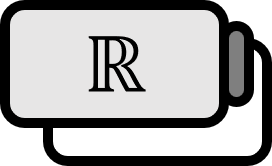解析学における微分の連鎖律
定理1
$f :[a,b] \to \mathbb{R}$が連続関数であり、$x\in [a,b]$で微分可能だとしよう。$g : f([a,b])\to \mathbb{R}$が$f (x)\in f([a,b])$で微分可能だとしよう。そして、$h : [a,b] \to \mathbb{R}$を次のようにする。
$$ h(t)=g\left( f(t) \right)\quad (a\le t \le b) $$
そうすると、$h$は$x$で微分可能であり、その値は以下の通りである。
$$ h^{\prime}(x)=g^{\prime}(f(x))f^{\prime}(x) $$ 合成関数記号を使用すると、次のようになる。 $$ ( g \circ f)^{\prime}(x)=g^{\prime}(f(x))f^{\prime}(x) $$
説明
この結果は一般に連鎖律と呼ばれる。
ここで、$f^{\prime}(x)$を内部微分とも呼ぶ。$y=f(x)$、$z=g(y)$と置いて、ライプニッツ記号で表すと、次のようになる。 $$ \frac{dz}{dx}=\frac{dz}{dy}\frac{dy}{dx} $$
ライプニッツ記号が便利な理由は、上の式の左辺がまるで右辺を約分したかのように見えるからである。$\dfrac{dy}{dx}$は「dxのdに対する割合」ではなく$y$の微分だが、それを分数として扱っても、その意味はピッタリ合っている。
証明
まず、以下のように関数$G$を定義しよう。
$$ G(f(t)) :=\begin{cases} \frac{g(f(x))-g(f(t))}{f(x)-f(t)} -g^{\prime}(f(x)) & f(t) \ne f(x) \\ 0 & f(t)=f(x)\end{cases},\quad (t\in[a,b]) $$
すると、すべての$f(t)$に対して、次が成り立つ。
$$ \lim \limits_{ f(s) \to f(t) } G(f(s))=G(f(t)) $$
これは連続の同値条件であるため、$G$は連続関数である。さらに、次が成り立つ。
$$ h(x)-h(t) = g(f(x))-g(f(t))=\Big( f(x)-f(t) \Big) \Big( g^{\prime}(f(x))+G(f(t)) \Big) $$
すると、極限の性質により、以下の式が成り立つ。
$$ \begin{align*} h^{\prime}(x) =&\ \lim \limits_{t \to x} \frac{ h(x)-h(t)}{x-t} \\ =&\ \lim \limits_{t \to x} \frac{ \Big( f(x)-f(t) \Big) \Big( g^{\prime}(f(x))+G(f(t)) \Big)}{x-t} \\ =&\ \lim \limits_{t \to x} \left[ g^{\prime}(f(x))\frac{ f(x)-f(t) }{x-t}+G(f(t))\frac{f(x)-f(t) }{x-t} \right] \\ =&\ \lim \limits_{t \to x} \left[ g^{\prime}(f(x))\frac{ f(x)-f(t) }{x-t}\right]+\lim \limits_{t \to x} \left[G(f(t))\frac{ f(x)-f(t) }{x-t} \right] \\ =&\ \lim \limits_{t \to x} g^{\prime}(f(x))\lim \limits_{t \to x}\frac{ f(x)-f(t) }{x-t}+\lim \limits_{t \to x}G(f(t))\lim \limits_{t \to x}\frac{ f(x)-f(t) }{x-t} \\ =&\ g^{\prime}(f(x))f^{\prime}(x)+0\cdot f^{\prime}(x) \\ =&\ g^{\prime}(f(x))f^{\prime}(x) \end{align*} $$
■
ウォルター・ルーディン, 数学分析の原理 (第3版, 1976), p105 ↩︎