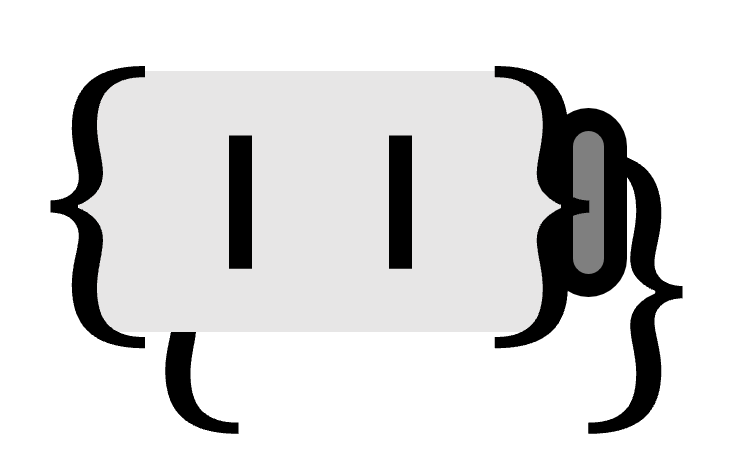選択公理
公理 1
$$ \forall U \left( \emptyset \notin U \implies \exists f : U \to \bigcup_{X \in U \\ f(X) \in X } U \right) $$ 空でない集合の集合 $U$ に対して、$U$ の各元から一つずつ要素を選ぶ選択関数 $f$ が存在する。
説明
選択公理は、例えば以下のような集合の集合 $U$ がある時、それぞれの集合から一つの要素を選ぶ関数 $f$ が存在することを保証してくれる。例を考えてみよう:
$$ U = \left\{ \left\{ \pi , 1/2 \right\} , \left\{ e , -42 \right\} , \left\{ 3/2, 1/7 , \sqrt{2} \right\} \right\} \\ f(X) = \begin{cases} \pi &, X = \left\{ \pi , 1/2 \right\} \\ e &, X = \left\{ e , -42 \right\} \\ \sqrt{2} &, X = \left\{ 3/2, 1/7 , \sqrt{2} \right\} \end{cases} $$ もちろん、$f$ の値域 $f(U) = \left\{ \pi , e, \sqrt{2} \right\}$ の存在は 置換公理形式によってもよくわかる。本当の問題は「これがなぜ公理でなければならないほど明らかでないのか」ということだ。上記の例をよく見ると、$f$ は与えられた有限集合から無理数のみを選択しているが、与えられた $U$ が何であれ、このような $f$ がうまく存在できるかどうかは全く別の問題だ。
もう少し難しい例で、実数集合 $\mathbb{R}$ に対して $U = 2^{\mathbb{R}} \setminus \emptyset$ を考えてみよう:
- 実数は常に序序の比較が可能であるため、おそらくその最小値$\min$が選択関数になりそうだが、区間 $(0,1] \in 2^{\mathbb{R}}$ の場合最小値が存在しないので選択関数になり得ない。
- $\inf$ は $0 \notin (0,1]$ であるため、選択関数になり得ないことは言うまでもない。
- 区間の長さ?$2^{\mathbb{R}}$ には 区間ではない集合も存在する。
- $X$ が有限集合なら$0$ に最も近い数を選び、無限集合なら整数集合 $\mathbb{Z}$ との交差を取って$0$ に最も近い数を選ぶ$g(X) = \begin{cases} \argmin_{x \in X } | x | &, |X| < \infty \\ \argmin_{x \in X \cap \mathbb{Z}} |x| &, | X | = \infty \end{cases}$は?$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$に対して定義できない。
… $U = 2^{\mathbb{R}} \setminus \emptyset$ だけでも選択関数を見つけるのは思ったほど簡単ではない。しかし、選択公理は選択関数がどのように見えるかはわからないが、とにかく存在すると断定する。具体的な$f$を提案できないで存在すると断言するのは、論理的にどれほど大胆なことか考えてみよう。選択関数の存在は本当に自明か?公理なしで自信を持って選択関数が存在すると言えるだろうか?もちろん、このポストを読んでいる誰かは$2^{\mathbb{R}} \setminus \emptyset$を見てすぐに素晴らしいアイデアを思いついたかもしれない。しかし、これは広大な数学の世界で非常に小さく、たった一つの例に過ぎない。どんなに天才でも、与えられたあらゆる奇想天外な集合に対して毎回選択関数を見つけ出す勇気はないだろう。選択公理の必要性を認め、受け入れよう。
同値 1
一方で、選択公理と同値である次の定理を紹介する。
- [1] ハウスドルフの極大原理: 部分順序集合 $(A, \le)$ の全順序部分集合の族を $\mathcal{F}$ とするとき、$\mathcal{F}$ での包含関係 $\subset$ を順序とする部分順序集合 $(\mathcal{F}, \subset)$ に極大元が存在する。
- [2] ツォルンの補題: 部分順序集合 $(A, \le )$ が全ての鎖に対して上界を持つならば、$A$ に極大元が存在する。
- [3] 整列定理: 空でない任意の集合は整列順序を持つ。
選択公理はハウスドルフの極大原理を含意し、ハウスドルフの極大原理はツォルンの補題を含意し、ツォルンの補題は整列定理を含意し、整列定理は選択公理を含意する。これらの定理は選択公理と同値だが、表現が少し違うだけで、用途が異なる。用途が異なるとは、単に何かを証明する際に選択公理を使用し、それにぴったりの同値を使用するということに過ぎない。特に、名高いツォルンの補題は、文字通りさまざまな分野で頻繁に使用される。