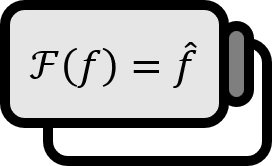定義
関数としてのフーリエ変換
関数 $f \in$ $L^{1}$のフーリエ変換Fourier transform of $f$を次のように定義する。
$$ \hat{f}(\xi) := \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i \xi t}dt $$
オペレーターとしてのフーリエ変換
次のように定義される作用素 $\mathcal{F} : L^{1} \to$ $C_{0}$をフーリエ変換という。
$$ \mathcal{F}[f] (\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i \xi t}dt $$
説明
定義にあるように、フーリエ変換という言葉はオペレーター $\mathcal{F}$ 自体を意味する場合もあり、または $\mathcal{F}$ の関数値 $\hat{f} = \mathcal{F}f = \mathcal{F}[f]$ を意味する場合もある。 $\mathcal{F}$ の共域が $C_{0}$ であることはリーマン・ルベーグ補題によって保証される。また、次が成り立つことを簡単に示すことができる。 $f \in L^{1}$について、
$$ \left\| \mathcal{F}f \right\|_{\infty} \le \left\| f \right\|_{1} $$
証明
$$ \begin{align*} \left\| \mathcal{F}f \right\|_{\infty} = \max\limits_{\xi \in \mathbb{R}} \left| \mathcal{F}f(\xi) \right| &= \max\limits_{\xi \in \mathbb{R}} \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i \xi t}dt \right| \\ &\le \max\limits_{\xi \in \mathbb{R}} \int_{-\infty}^{\infty} \left| f(t) e^{-i \xi t} \right| dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left| f(t) \right| dt = \left\| f \right\|_{1} \end{align*} $$
フーリエ変換は積分変換の一種であり、この逆変換は次の通りである。
$$ f(t) = \mathcal{F}^{-1}\hat{f}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{i t \xi} d \xi $$
最初の定数 $\dfrac{1}{2\pi}$はどこに置いても構わないため 逆変換の前に書くことも、変換の前に書くこともある。あるいは、両方に $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ を置くこともある。これは著者の便宜によるだけであり、本質的には違いがない。また、定義を見れば $f$ が積分可能で、すなわち $f\in L^{1}$ の条件を満たす必要があることが分かる。 $\hat{f}$ も積分可能であればフーリエ逆変換もよく定義される。
多変数関数のフーリエ変換
多変数関数のフーリエ変換は次のように定義する。多変数関数 $f \in L^{1}(\mathbb{R}^{n})$ のフーリエ変換は、
$$ \mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi}):=\int f(x)e^{-i \boldsymbol{\xi} \cdot \mathbf{x} }d\mathbf{x} $$
$$ \mathcal{F} f(\xi_{1},\ \cdots ,\ \xi_{n}) := \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_{1},\ \cdots,\ x_{n})e^{-i(\xi_{1} x_{1}+\cdots+\xi_{n} x_{n})}dx_{1}\cdots dx_{n} $$
表記法
$f$ のフーリエ変換でよく使う二つの表記法がある。
$$ \mathcal{F}(f),\quad \hat{f} $$
教科書では、著者の好む記号が何かによって異なるが、どちらもよく使われる。右側のハット記号を使う方が便利そうに見えるが、誤解される恐れがあるため、正確に記載すべき場合は左側の表現を使う方が良い。例えばインプット関数自体の記号が長くなる場合、ハット記号を使うと混乱しやすく見栄えもよくない。この場合には $\mathcal{F}$ を使うと、式が意味するところを正確かつ明瞭に示すことができる。例えば $W_{c}f$ のフーリエ変換は以下に示すように $\mathcal{F}$ で表記する方が良い。
$$ \mathcal{F}(\mathcal{W}_{c}f),\quad \hat{\mathcal{W}_{c}f},\quad \widehat{\mathcal{W}_{c}f} $$
ただし、混乱の恐れがない場合はハット記号が便利だ。このように同じ概念について様々な表記法があるのは微分でも同様である。
$$ f^{\prime}, \quad \dfrac{df}{dx} $$
$\hat{f}$と$\mathcal{F}$の二つの表記法の長所と短所は、ちょうど微分に関して左のニュートン表記法が経済性と利便性に優れる一方、右のライプニッツ表記法が連鎖律などを計算する際の正確性と厳密性に優れるのに似ている。
導出1
有限な区間を周期とする(=有限な区間で定義された)関数はフーリエ級数を用いて近似することができる。これは有用だが周期関数に対してのみ使用できるため、非周期関数に対しても同様の役割を果たす道具が必要である。こうしたアイデアから生まれたのがフーリエ変換Fourier transformである。フーリエ変換を導出する過程では、非周期関数を実数全体の区間を周期とする、周期が数直線全体にわたって1回繰り返される関数とみなすことが核心のアイデアである。
$f$を区間$[-L,L)$で定義された関数とする。すると$f$のフーリエ級数と複素フーリエ係数は次のようになる。
$$ \begin{equation} f(t)=\sum \limits_{n=-\infty}^{\infty} c_{n} e^{i\frac{n\pi t}{L}} \end{equation} $$
$$ c_{n} = \dfrac{1}{2L}\int_{-L}^{L}f(t)e^{-i\frac{n \pi t}{L} }dt $$
次のような変数変換を行う。
$$ \Delta \xi = \dfrac{\pi}{L},\quad \xi_{n}=n\Delta\xi=\dfrac{n\pi}{L} $$
すると$(1)$は次のようになる。
$$ f(t) = \sum \limits_{n=-\infty}^{\infty} c_{n} e^{i\xi_{n} t}, \quad c_{n} = \dfrac{1}{2L}\int_{-L}^{L}f(t)e^{-i \xi_{n} t }dt $$
$f(t)$に適切な定数を掛けて$c_{n}$の積分項を$\hat{f}(\xi_{n})$とすれば
$$ f(t)=\dfrac{L}{\pi}\sum \limits_{n=-\infty}^{\infty} c_{n} e^{i\xi_{n} t}\Delta \xi , \quad c_{n} = \dfrac{1}{2L}\hat{f}(\xi_{n}) $$
そして$f(t)$が$t \rightarrow \pm \infty$であるとき、速やかに$0$に収束すると仮定する。すると$c_{n}$について積分区間を$[-L,L)$から$(-\infty,\infty)$に拡張しても元の$c_{n}$と大差はないだろう。
$$ c_{n} \approx \dfrac{1}{2L} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\xi_{n} t}dt $$
これは$\xi_{n}$だけの関数であるため$c_{n} = \frac{1}{2L}\hat{f}(\xi_{n})$と呼ぶ。$f(t)$に代入すると
$$ f(t) \approx \dfrac{1}{2 \pi}\sum \limits_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi_{n}) e^{i\xi_{n} t}\Delta \xi $$
これはリーマン和に非常に似ている。ここで$L\rightarrow \infty$の極限を取れば$\Delta\xi \rightarrow 0$となり、上記の式の$\approx$は等式になり、和は積分になる。
$$ f(t) = \dfrac{1}{2 \pi}\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{i\xi t} d\xi \quad \text{and} \quad \hat{f}(\xi)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\xi t}dt $$
このとき$\hat{f}$を$f$のフーリエ変換と呼び、$f$を$\hat{f}$のフーリエ逆変換Fourier inverse transformと呼ぶ。
関連項目
- 確率変数の特性関数: 形式的に、確率変数の特性関数はフーリエ逆変換と見なすことができる。
Gerald B. Folland, Fourier Analysis and Its Applications (1992), p204-205 ↩︎