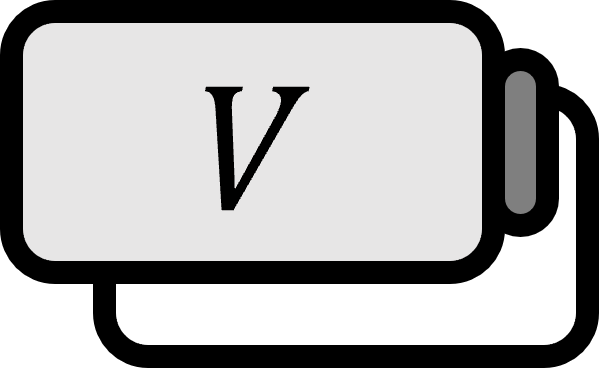ベクトル空間における直和
定義
ベクトル空間 $V$ の二つの部分空間 $W_{1}$と$W_{2}$に対して、次のことを満たせば、$V$を$W_{1}$と$W_{2}$の直和direct sumと呼び、$V = W_{1} \oplus W_{2}$と表記する。
(i) 存在性: 任意の$\mathbf{v} \in V$に対して、$\mathbf{v} = \mathbf{v}_{1} + \mathbf{v}_{2}$を満たす$\mathbf{v}_{1} \in W_{1}$と$\mathbf{v}_{2} \in W_{2}$が存在する。
(ii) 排他性: $W_{1} \cap W_{2} = \left\{ \mathbf{0} \right\}$
(iii) 一意性: 与えられた$\mathbf{v}$に対して、$\mathbf{v} = \mathbf{v}_{1} + \mathbf{v}_{2}$を満たす$\mathbf{v}_{1} \in W_{1}$と$\mathbf{v}_{2} \in W_{2}$は一意である。
一般化1
$W_{1}, W_{2}, \dots, W_{k}$をベクトル空間 $V$の部分空間としよう。これらの部分空間が次の条件を満たすとき、$V$を$W_{1}, \dots, W_{k}$たちの直和と呼び、$V = W_{1} \oplus \cdots \oplus W_{k}$と表記する。
$\displaystyle V = \sum\limits_{i=1}^{k}W_{i}$
$\displaystyle W_{j} \bigcap \sum\limits_{i \ne j}W_{i} = \left\{ \mathbf{0} \right\} \text{ for each } j(1\le j \le k)$
このとき、$\sum\limits_{i=1}^{k}W_{i}$は$W_{i}$たちの和である。
解説
(i) 存在性: この条件は$V = W_{1} + W_{2}$、つまり「$V$は$W_{1}$と$W_{2}$の和である」と書き換えることができる。
(iii) 一意性: 実際、この条件は必要ない。条件**(ii)**により$\mathbf{v}_{1} \in W_{1}$であれば、$\pm \mathbf{v}_{1} \notin W_{2}$であり、$W$のゼロベクトルに対して次の表現だけが存在する。
$$ \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0},\quad \mathbf{0}\in W_{1}, W_{2} $$
したがって、$\mathbf{v}$に対して、二つの表現$\mathbf{v}_{1} + \mathbf{v}_{2}$と$\mathbf{v}_{1}^{\prime} + \mathbf{v}_{2}^{\prime}$が存在するならば、
$$ \mathbf{0} = \mathbf{v} - \mathbf{v} = (\mathbf{v}_{1} - \mathbf{v}_{1}^{\prime}) + (\mathbf{v}_{2} - \mathbf{v}_{2}^{\prime}) = \mathbf{0} + \mathbf{0} \implies \mathbf{v}_{1}=\mathbf{v}_{1}^{\prime},\ \mathbf{v}_{2}=\mathbf{v}_{2}^{\prime} $$
さらに、(i), (ii) $\iff$ (iii) が成り立つ。
定義を見ただけでは把握しづらいが、ユークリッド空間での例を見れば、これが非常に理にかなった便利な概念であることがわかる。例えば、$\mathbb{R}^{3} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$を考えると、$\mathbb{R}^{3}$の要素は$3$次元ベクトル$(x,y,z)$であるが、これを$(x,y)$と$(z)$に分けてみよう。
一方で、分けたものを再結合する過程を考えれば、$(x,y) \in \mathbb{R}^2$となり、それによって$(z) \in \mathbb{R}$となるため、これらの単純な和集合$\mathbb{R}^2 \cup \mathbb{R}$は、スカラーと$2$次元ベクトルを要素に含むことになる。これらの記号だけでは、実際に私たちが望む空間の拡張と分離を表現するのが難しいことがわかる。だから、直和という概念を導入すると、部分空間がベクトル空間をきれいに分割するときに、多くの面で説明しやすくなるだろう。
参照
Stephen H. Friedberg, Linear Algebra (第4版, 2002), p275 ↩︎