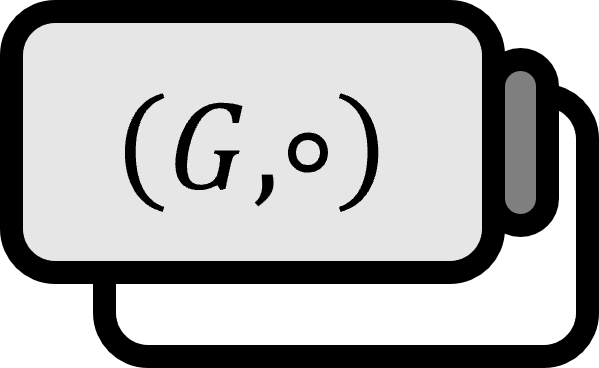一意因数分解整域
定義 1
- 整域 $D$ の$0$でもなく単元もない全ての要素に対して有限素因数分解が一意に存在する場合、$D$を一意素因数分解整域uFDという。
- 一意素因数分解整域 $D$ の $a_{1} , \cdots , a_{n}$ に対して$d \mid a_{i}$であり、$a_{i}$の全ての約数が$d$を割る場合、$d$を$a_{1} , \cdots , a_{n}$の最大公約数greatest Common Divisorといい、$\gcd$と書く。
- 一意素因数分解整域 $D$ のある多項式を$f(x) := a_{0} + a_{1} x + \cdots + a_{n} x^{n}$とする。$\gcd ( a_{0} , a_{1} , \cdots , a_{n} ) = 1$の場合、$f(x) \in D [ x ]$を原始的primitiveという。
定理 2
- [2] 算術の基本定理:$\mathbb{Z}$はUFDである。
- [3] ガウスの補助定理:$D$がUFDであれば、$D [ x ]$の原始多項式たちの積も原始的である。
- [4]: $D$がUFDであれば、$D [ x ]$もUFDである。
- [5]: $F$が体であれば、$F[ x_{1} , \cdots , x_{n} ]$はUFDである。
説明
「一意素因数分解整域」という言葉は通常、長いためによくUFDという略語が使われる。
UFD
要素の有限素因数分解が存在することは、与えられた要素が有限数の既約元の積で表されることを意味する。UFDが便利である理由は、より大きなオブジェクトを分割して考えることができるようになるためである。定義上その要素が何であるかは指摘できなくても、そのような素因数分解が存在するだけで大いに役立つ。これにより、我々が考える「常識的な」計算が成り立つ整域となる。
UFDの例は非常に多い。例えば、定理 [2] で言及されているように、整数環$\mathbb{Z}$がそうである。しかし、整数環に$\sqrt{-5}$を加えた単純拡大体$\mathbb{Z} ( \sqrt{ - 5 } )$を考えてみよう。ここで、$21 \in \mathbb{Z} ( \sqrt{ - 5 } )$は素因数分解$21 = 3 \cdot 7$を持つ一方で、$21 = ( 1 + 2 \sqrt{-5}) ( 1 - 2 \sqrt{-5}) $も可能であり、一意ではないため、$\mathbb{Z} ( \sqrt{ - 5 } )$が一意素因数分解整域でないことが容易に確認できる。
原始的関数?
関数が原始的であるとは、積分学における原始関数とは全く関係なく、$(3 x^2 + 6 x + 3) \in \mathbb{Z} [ x ]$が$3 ( x^2 + 2x + 1)$のように全体を$3$で囲むこととは異なり、係数を囲むことができない関数を指す。
算術の基本定理
整数論におけるステートメントとは異なり、整数環$\mathbb{Z}$がUFDであることを要約したものである。もちろん、この宣言のためには無数の概念が動員されているが、高度な整数論ではこのように代数の言葉で表現されることが多いため、代数学の学習は不可欠である。代数学を専攻しなくても、代数学の知識がなければ理解が難しい。
ガウスの補助定理
ガウスの補助定理は思っているよりも面白い定理である。例えば、$(5x + 1) , (2x^2 + 3x + 1) \in \mathbb{Z} [ x ]$を考えると、その積は$( 10 x^3 + 17 x^2 + 8 x + 1 )$であり、一見するといかなる最大公約数$a \in \mathbb{Z}$で囲むこともできない。一つくらいは反例が見つかりそうだが、ガウスの補助定理のおかげで、そうした無駄な努力をする必要はなくなる。
証明
1
Part 1. 存在性
$D$がPIDである場合、$d \in D$は既約元$p_{1} , \cdots , p_{r}$たちの有限積$a = p_{1} \cdots p_{r}$として表現される。
Part 2. 一意性
別の既約元$q_{1} , \cdots , q_{s}$に対して$a = q_{1} \cdots q_{s}$も可能であるとしよう。
PIDの既約元は素元であるため、ある$1 \le j \le s$に対して$p_{1} \mid q_{j}$でなければならない。 $$ p_{1} p_{2} \cdots p_{r} = p_{1} u_{1} q_{2} \cdots q_{s} $$ 両辺から$p_{1}$を取り除くと $$ p_{2} \cdots p_{r} = u_{1} q_{2} \cdots q_{s} $$ 同じ方法で$i=r$まで繰り返すと $$ 1 = u_{1} \cdots u_{r} q_{r+1} \cdots q_{s} $$ を得る。$q_{r+1} \cdots q_{s}$は既約元であるため、$r=s$を割る必要がある。
■
[2]
$\mathbb{Z}$の全てのイデアルは$\left< n \right> = n \mathbb{Z}$の形であるためPIDであり、定理 1 によってUFDである。
■
[3]
$$ \begin{align*} f(x) &:= a_{0} + a_{1} x + \cdots + a_{n} x^n \\ g(x) &:= b_{0} + b_{1} x + \cdots + b_{m} x^m \end{align*} $$ 原始多項式$f(x) , g(x) \in D[x]$を上記のように表わそう。
$p \in D$を既約元としよう。
- $f(x)$は原始的であるため$\gcd ( a_{0} , \cdots , a_{n} ) = 1$であり、$p$が$a_{0} , \cdots , a_{n}$を全て割ることはできない。それに$i = 0, 1 , \cdots , n$に対して$p$が$a_{i}$を割ることができない最初の係数を$a_{r}$としよう。
- $g(x)$も原始的であるため$\gcd ( b_{0} , \cdots , b_{m} ) = 1$であり、$p$が$b_{0} , \cdots , b_{m}$を全て割ることはできない。それに$j = 0, 1 , \cdots , m$に対して$p$が$b_{j}$を割ることができない最初の係数を$b_{s}$としよう。
すると、$f(x)g(x)$の$( r + s)$次の項の係数は $$ c_{r+s} = ( a_{0} b_{r+s} + \cdots + a_{r-1} b_{s+1} ) + a_{r} b_{s} + ( a_{r+1} b_{s-1} + \cdots + a_{r+s} b_{0} ) $$ となり、
- $a_{r}$の定義によれば $$ p \mid ( a_{0} b_{r+s} + \cdots + a_{r-1} b_{s+1} ) $$
- $b_{s}$の定義によれば $$ p \mid ( a_{r+1} b_{s-1} + \cdots + a_{r+s} b_{0} ) $$
である。しかし、$p \nmid a_{r} b_{s}$であるため、与えられた$p$は$f(x) g(x)$を割ることができない。これは全ての既約元についても同様であるため、$f(x) g(x)$は原始的である。
■
[4]
$f(x) \in D[x]$の次数を$n$としよう。
すると、$f(x)$は $$ f (x) = g_{1} (x) \cdots g_{r} (x)) $$ のように因数分解できる。また、$i = 1 , \cdots , r$に対して、それぞれの因数を原始関数$h_{i} (x) \in D[x]$と$c_{i} \in D$の積である $$ g_{i} (x) = c_{i} h_{i} (x) $$ として表わすことができる。このような$c_{i}$を$g_{i} (x)$のコンテントcontentと