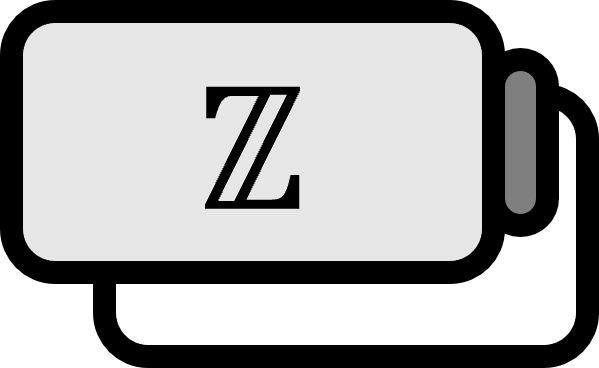合同方程式に対する代数学の基本定理の証明
定理 1
ある素数$p$について$p\nmid a_{ 0 }$とすると、全ての係数が整数の多項式 $$ f(x)=a_{ 0 }x^{ d }+a_{ 1 }x^{ d-1 }+ \cdots +a_{ d-1 }x+a_{ d } $$ に対して方程式 $f(x)\equiv 0 \pmod{p}$は、せいぜい$d$個の合同でない解を持つ。
解説
皆がよく知っているように、実係数の多項式について話すならば、$n$次方程式は重根を含めて$n$個の解を持つというのが定理だ。これを数論で考えると$\pmod{p}$において整数の係数のみを持つ$d$次方程式はせいぜい$d$個の解しか持たないと言える。このようなステートメントは整数に複素数を導入することでさらに簡潔に変わることができる。
証明
戦略:代数学の基本定理が複素解析を通じて導出される一方で、合同方程式に関しては初等的な数論知識で十分である。合同でない解が$d$個よりも多く存在すると仮定して矛盾を導く。
方程式$P(x)\equiv 0 \pmod{p}$において、異なる解が$n$よりも多く存在するような$n$次の整数係数多項式$P$が存在すると仮定する。その中で、最小の次数の多項式$f$を選ぶと、以下のように表せる。 $$ f(x)=A_{ 0 }x^{ d }+A_{ 1 }x^{ d-1 }+ \cdots +A_{ d-1 }x+A_{ d } (p\nmid A_{ 0 }) $$ すると、方程式$f(x)\equiv 0 \pmod{p}$は異なる解$r_{ 1 },r_{ 2 }, \cdots ,r_{ d },r_{ d+1 }$を持つ。$f(x)\equiv 0 \pmod{p}$の解$r$に対して $$ f(x)=(x-r)g(x)+f(r) $$ と表される。$f(x)$を$(x-r)$で割った商の$g(x)$は、以下のような$(d-1)$次の整数係数多項式である。 $$ g(x)=B_{ 0 }x^{ d-1 }+B_{ 1 }x^{ d-2 }+ \cdots +B_{ d-2 }x+B_{ d-1 } (p\nmid B_{ 0 }) $$ $r$に$r_{ 1 }$を代入すると$f(r_{ 1 })\equiv 0 \pmod{p}$となり $$ f(x)\equiv (x-r_{ 1 })g(x) \pmod{p} $$ $r_{ k }$は$f(x)=0$の根であるから、$(2\le k\le d+1)$に対して $$ f(r_{ k })\equiv (r_{ k }-r_{ 1 })g(r_{ k })\equiv 0 \pmod{p} $$ $r_{ k }-r_{ 1 } \not\equiv 0 \pmod{p}$であるから、$g(r_{ k })\equiv 0 \pmod{p}$である必要がある。したがって、$g(x)\equiv 0 \pmod{p}$は$d$個の異なる解$r_{ 2 },r_{ 3 }, \cdots ,r_{ d+1 }$を持つ。$f(x)$は、次元よりも多くの異なる解を持つ多項式の中で最も低い$d$次の多項式であるが、$g(x)$が$(d-1)$次でありながらも$d$個の異なる解を持っているので矛盾である。
■
関連項目
Silverman. (2012). A Friendly Introduction to Number Theory (4th Edition): p60. ↩︎