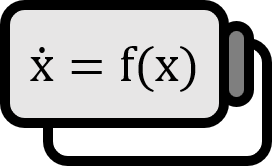類似性次元
定義
集合 $\displaystyle A := \lim_{n \to \infty} A_{n}$ が 自己相似集合と仮定する。 $A_{1}$ が持つ $A_{0}$ と類似の部分集合を $A_{0}$ のコピーcopy of $A_{0}$ と呼ぶとき、 $A_{0}$ のコピーの ボリュームvolume を $r$倍して $A_{0}$ のボリュームと等しくなる $r$ を スケールファクターscale factor と呼ぶ。 $A_{1}$ が 互いに素 の $A_{0}$ のコピーを $m$ 個持つとき、次のように定義された $d$ を 相似次元similarity dimension とする1。 $$ d := {\frac{ \log m }{ \log r }} $$ ここで、ボリュームとは長さ、面積、体積などを指す。
説明
相似次元とは フラクタル次元 の一種であり、幾何学的なセンスで自然に定義される。概念を直感的に理解できる例として、次のように正方形の各辺を $n$ 等分して新しい線分を引く図形を想像してみよう。

辺の長さを $2$ 等分すると生まれる新しい正方形の長さは既存の $1/2$ になり、そのような小さな正方形が $4$ 個生まれる。 同様に、辺の長さを $3$ 等分すると、当然これまでの $1/3$ の正方形が $9$ 個生まれる。相似次元の定義ではスケールファクターはこのように縮小する長さの逆数である $r = n$ とみなせ、コピーの数は $m = n^{2}$ であることが確認されるのは難しくない。それによれば、正方形の相似次元は $$ d = {\frac{ \log m }{ \log r }} = {\frac{ \log n^{2} }{ \log n }} = 2 $$ と計算され、正方形の相似次元は $2$ であると言える。これは私たちが正方形を $2$ 次元の図形と認識する常識と一致する。驚くこともなく、これは一般的なハイパーキューブ $[0, 1]^{d}$ に対しても一貫して成立する。
カントール集合

カントール集合 は線分の長さが $1/3$ に縮小される代わりに、そのような線分が $2$ 個生まれる。 $r = 3$であり、 $m = 2$であるため、カントール集合の相似次元は次のように計算される。 $$ d = {\frac{ \log m }{ \log r }} = {\frac{ \log 2 }{ \log 3 }} \approx 0.63 $$ これは長さの合計が $0$でありながら 非可算集合 であり、完全な線分でもないため、カントール集合が $0$ 次元と $1$ 次元の間のどこかの次元を持つかのように感じさせる。
コッホ曲線

コッホ曲線 は線分の長さが $1/3$ に縮小される代わりに、そのような線分が $4$ 個生まれる。 $r = 3$で、 $m = 4$であるため、コッホ曲線の相似次元は次のように計算される。 $$ d = {\frac{ \log m }{ \log r }} = {\frac{ \log 4 }{ \log 3 }} \approx 1.26 $$ コッホ曲線の長さは無限だが、それでもこれほど極端に折れ曲がるところで面積が生まれる理由もない。この結果は、コッホ曲線が $1$ 次元よりは大きく、 $2$ 次元よりは小さい次元に置かれることを直感的に示している。
限界
相似次元の例を見てフラクタルについてある程度の感を掴めたなら良いことだが、残念ながら今後の人生で相似次元というものを再び見る機会はほとんどない。コンピュータの計算を借りずに正確な値を計算できるのは良いが、そもそも厳密な定義を下しにくい自己相似集合を、それも明確な規則を持つ場合にのみ言及できるからだ。現実世界でデータとして与えられる幾何学的な要素に対してはこのような規則を知ることができないため、相似次元は教科書的な概念としてとどまることになる。
参照項目
Strogatz. (2015). Nonlinear Dynamics And Chaos: With Applications To Physics, Biology, Chemistry, And Engineering(2nd Edition): p406. ↩︎