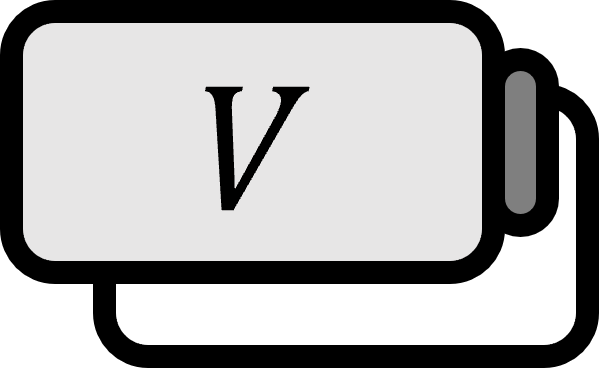몫공간의 기저와 차원
定理1
$V$を$n$次元ベクトル空間、$W \le V$を$k (\lt n)$次元部分空間とする。$W$の基底を$\left\{ u_{1}, \dots, u_{k} \right\}$とする。そしてこの基底を拡張した$V$の基底を$\left\{ u_{1}, \dots, u_{k}, u_{k+1}, \dots, u_{n} \right\}$とする。すると
$\left\{ u_{k+1} + W, \dots, u_{n} + W \right\}$は商空間 $V/W$の基底である。
$\dim(V) = \dim(V/W) + \dim(W)$
説明
次元に関する結果は別の証明によっても得られる。商空間という名前の由来や、$V / W$のように表記する理由が直観的に分かる定理である。ベクトル空間の次元は$\mathbb{R}^{n}$のように指数の形で書かれるが、商空間の次元は実際に割り算を通じて指数法則により指数を引くように計算されることを示す。$V = \mathbb{R}^{5}$、$W = \mathbb{R}^{2}$とすると、
$$ V/W = \dfrac{V}{W} = \dfrac{\mathbb{R}^{5}}{\mathbb{R}^{2}} = \mathbb{R}^{5-2} = \mathbb{R}^{3} $$
証明
$\beta = \left\{ u_{k+1} + W, \dots, u_{n} + W \right\}$とする。
$\beta$は線形独立である。
$V/W$の零ベクトルは $W$であるので、次の式が成立するような解は$a_{k+1} = \cdots = a_{n} = 0$のみであることを示さねばならない。
$$ a_{k+1}(u_{k+1} + W) + \cdots + a_{n}(u_{n} + W) = W $$
$V/W$で定義された加法に従って、
$$ \begin{align*} a_{k+1}(u_{k+1} + W) + \cdots + a_{n}(u_{n} + W) &= (a_{k+1}u_{k+1} + \cdots + a_{n}u_{n}) + W \\ &= W \end{align*} $$
(b) $v_{1}, v_{2} \in V$に関して、$v_{1} + W = v_{2} + W$であることは$v_{1} - v_{2} \in W$であることと同値である。
(c) $V/W$はベクトル空間であり、零ベクトルは$0_{V} + W = W$である。($0_{V}$は$V$の零ベクトルである。)
すると上の補助定理により次を得る。
$$ (a_{k+1}u_{k+1} + \cdots + a_{n}u_{n}) + W = 0_{V} + W $$ $$ \implies a_{k+1}u_{k+1} + \cdots + a_{n}u_{n} - 0_{V} = a_{k+1}u_{k+1} + \cdots + a_{n}u_{n} \in W \tag{1} $$
$u_{k+1}, \dots, u_{n}$は定義により明らかに$W$の元ではない。
$$ u_{k+1}, \dots, u_{n} \notin W \tag{2} $$
ところが$u_{k+1}, \dots, u_{n}$は線形独立であるため、$(1)$と$(2)$を同時に満たすには$a_{k+1}u_{k+1} + \cdots + a_{n}u_{n} = 0_{V} = 0_{W}$でなければならない。したがって次を得る。
$$ a_{k+1} = \cdots = a_{n} = 0 $$
$\span \beta = V/W$
$w \in W$に対して$w + W = W$であるので、任意の $v \in V$ に対して、
$$ \begin{align*} v + W &= (a_{1}u_{1} + \cdots + a_{k}u_{k} + a_{k+1}u_{k+1} + \cdots + a_{n}u_{n}) + W \\ &= (a_{k+1}u_{k+1} + \cdots + a_{n}u_{n}) + W \\ &= (a_{k+1}u_{k+1} + W) + \cdots + (a_{n}u_{n} + W) \\ \end{align*} $$
ゆえに $\beta$ は $V/W$ の基底である。したがって
$$ \begin{align*} \dim(V) &= \dim(V/W) + \dim(W) \\ n &= (n-k) + k \end{align*} $$
■
Stephen H. Friedberg, Linear Algebra (4th Edition, 2002), p58 ↩︎