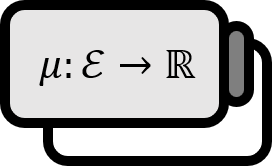局所積分可能な関数の平均値は中心の関数値に収束する。
定理1
$f \in L^1_{\mathrm{loc}}$としよう。すると、次のことが成り立つ。
$$ \lim \limits_{r \rightarrow 0} A_{r} f(x)=f(x) \text{ a.e. } x\in \mathbb{R}^n $$
ここで、$\text{ a.e. }$はほぼ至る所でである。
説明
ここでのメッセージは、局所的に積分可能な関数の$B(r,x)$での体積上の平均値が半径$0$に近づく極限は、体積の中心の関数値と等しいということである。
証明
体積の半径が$0$に近づく極限をとるために、ある$N \in \mathbb{N}$に対して次の式が成立することを示せば十分である。
$$ A_{r}f(x) \rightarrow f(x) \text{ a.e. } |x|\le N $$
同じ理由で、$r<1$の場合だけ考えればよい。すると、以下の図に示されるように、$|x| \le N$であり、$r<1$のとき、$A_{r} f(x)=\frac{1}{m\big( B_{r}(x) \big)}{\displaystyle \int_{B_{r}(x)}} f(y)dy$は、$f(y)$である$|y|\le N+1$によってのみ決定される。したがって、$f$を$f\chi_{B(N+1,x)}$に置き換えることができ、$f\in L^1$と仮定してもよい。

補助定理
$f \in L^1(m)$であり、かつ$\epsilon>0$としよう。すると、以下の条件を満たすシンプルな関数$\phi=\sum\nolimits_{1}^Na_{j}\chi_{R_{j}}$が存在する。
$$ \int |f-\phi| <\epsilon $$
さらに、以下の条件を満たす有界な集合の外では関数値が$0$である連続関数$g$が存在する。
$$ \int |f-g| <\epsilon $$
$m$はルベーグ測度である。
今、$\epsilon>0$が与えられたとしよう。すると、$f \in L^1$であるため、補助定理により、以下の条件を満たす連続な積分可能な関数$g$が存在する。
$$ \int |g(y)-f(y)|dy < \epsilon $$
さらに、$g$が連続であるため、全ての$x\in \mathbb{R}^n$、$\delta >0$に対して、以下の条件を満たす$r>0$が存在する。
$$ |y-x|<r \implies |g(y)-g(x)| < \delta $$
また、$\frac{1}{m \big( B(r,x)\big)} {\displaystyle \int_{B(r,x)} }dy=1$であるため、$|y-x|<r$のときいつでも、以下が成立する。
$$ \begin{align*} |A_{r} g(x)-g(x)| &= \left| \frac{1}{m\big( B(r,x)\big)}\int_{B(r,x)}g(y)dy -g(x) \right| \\ &= \left| \frac{1}{m\big( B(r,x)\big)}\int_{B(r,x)}g(y)dy -\frac{1}{m\big( B(r,x)\big)}\int_{B(r,x)}g(x)dy \right| \\ &\le \frac{1}{m\big( B(r,x)\big)}\int_{B(r,x)}|g(y)-g(x)|dy \\ &\le \frac{1}{m\big( B(r,x)\big)}\int_{B(r,x)} \delta dy \\ &= \delta\frac{1}{m\big( B(r,x)\big)}\int_{B(r,x)} dy \\ &= \delta \end{align*} $$
したがって、$\lim \limits_{r \rightarrow 0} |A_{r} g(x) -g(x)|=0$である。三角不等式により、以下が成立する。
$$ \begin{equation} \begin{aligned} & \limsup \limits_{r\rightarrow 0} |A_{r}f(x)-f(x)| \\ \le& \limsup \limits_{r\rightarrow 0} \Big( |A_{r}f(x)-A_{r} g(x)|+|A_{r}g(x)-g(x)|+|g(x)-f(x)| \Big) \\ =&\ \limsup \limits_{r\rightarrow 0} H(f-g)(x)+ |g(x)-f(x)| \end{aligned} \end{equation} $$
次に、$E_\alpha$、$F_\alpha$を以下のように考えよう。
$$ E_\alpha =\left\{ x\ :\ \limsup\limits_{r \rightarrow 0} |A_{r} f(x)-f(x) | > \alpha \right\} \\ F_\alpha =\left\{ x\ :\ |g-f |(x) > \alpha \right\} $$
すると、$(1)$により、以下が成立する。
$$ E_\alpha \subset \Big( F_{\alpha /2} \cup \left\{ x\ :\ H(f-g)(x) >\alpha /2\right\} \Big) $$
$E_\alpha$に属する要素は、$F_{\alpha/2}$または$\left\{x\ :\ H(f-g)(x)>\alpha/2 \right\}$のいずれかに必ず属していなければならないため、以下が成立する。
$$ m(E_\alpha) \le m(F_{\alpha/2}) + m\Big( \left\{ x\ :\ H(f-g)(x)>\alpha/2\right\}\Big) $$
また、$F_{\alpha /2}$の定義により、以下が成立する。
$$ \begin{align*} && m(F_{\alpha /2}) \frac{\alpha}{2} & \le \int_{F_{\alpha /2}}|g-f|(x)dx < \epsilon \\ \implies && m(F_{\alpha/2}) &< \frac{2\epsilon}{\alpha} \end{align*} $$
さらに、マキシマル定理により、以下が成立する。
$$ m\Big( \left\{ x\ :\ H(f-g)(x) > \alpha/2 \right\} \Big) \le \frac{2C}{\alpha} \int|g-f|(x)dx \le \frac{2C\epsilon}{\alpha} $$
したがって、以下の結果を得る。
$$ m(E_\alpha) \le \frac{2\epsilon}{\alpha}+\frac{2C\epsilon}{\alpha}=\left( \frac{2(1+C)}{\alpha}\right)\epsilon $$
これはあらゆる$\epsilon>0$に対して成立するため、以下を得る。
$$ m( E_\alpha)=0 $$
$$ \lim \limits_{r\rightarrow R}\phi (r)=c \iff \limsup \limits_{r\rightarrow R}|\phi (r)-c|=0 $$
したがって、$\mathrm{a.e.}$ $x\in\mathbb{R}^n$に対して、以下を得る。
$$ \begin{align*} && \limsup \limits_{r\rightarrow 0} |A_{r} f(x)-f(x)| &= 0 \\ \implies && \lim \limits_{r \rightarrow 0}A_{r}f(x) &= f(x) \end{align*} $$
■
Gerald B. Folland, Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications (2nd Edition, 1999), p97 ↩︎