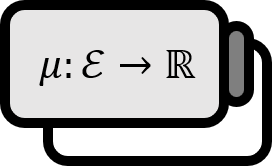正の集合, 負の集合, 零の集合
定義1
$\nu$を$(X,\mathcal{E})$上の符号測度としよう。そして$E,F \in \mathcal{E}$としよう。すると
$\nu (F) \ge 0,\ \forall F\subset E$の時、$E$を$\nu$に対する正集合positive setまたは単にポジティブpositiveという。
$\nu (F) \le 0,\ \forall F\subset E$の時、$E$を$\nu$に対する負集合negative setまたは単にネガティブnegativeという。
$\nu (F)=0,\ \forall F\subset E$の時、$E$を$\nu$に対する零集合null setまたは**$\nu$-ヌル**$\nu$-nullという。
説明
定義によると、零集合は同時に正集合であり、負集合である集合だ。正集合、負集合の定義を誤解しやすいので、正しく理解することが重要だ。$\mu (E)>0$の時、$E$を正の集合と呼ぶわけではない。$E$の全ての可測な部分集合$F\in\mathcal{E}$に対して$\mu (F) \ge 0$が成り立つ必要があって初めて、$E$を正の集合と呼ぶ。もちろん、この条件を満たすならば自然と$\nu (E) >0$が成り立つ。要約すると以下の通り。
$$ E\ \mathrm{is\ positive\ set\ for\ }\nu \implies \nu (E)>0 \\ \nu (E)>0 \not\implies E\ \mathrm{is\ positive\ set\ for\ }\nu $$
これは負集合、零集合に対しても同様だ。上述の話は符号測度にのみ適用される。絶対測度については少し話が異なる。$\mu$を絶対測度とした時、常に$0$以上の関数値を持つので、$\mu (E)=0$が$E$が$\nu$-ヌルであることと同値だ。正集合に関する話も同様だ。したがって、絶対測度に対しては、正集合、零集合という言葉を特に使う必要はない。下の図を見よう。

関数$f$を区間$E_2$でリーマン積分すると、その値は確かに正だが、$E_2$を正の集合とは呼ばない。上の図の例で、関数値が0より小さい部分が一点もない区間が正の集合だ。上の図で、$E_{1}$、$E_{3}$が正の集合で、$E_{5}$が負の集合だ。$E_2$、$E_{4}$は正の集合でも、負の集合でも、零集合でもない。最も重要な点は、ある$E \in \mathcal{E}$が必ずしも正集合であるか、または負集合である必要がないことだ。
定理
(a) 正の集合の可測部分集合も正の集合である。
(b) 任意の正の集合の可算和も正の集合である。
証明
(a)
正の集合の定義により自明だ。
(b)
$P_{1},\ P_2,\ \cdots$を正の集合としよう。そして$Q_{n}$を以下のように定義しよう。
$$ Q_{1}=P_{1},\quad Q_{n}=P_{n}-\left( \bigcup \nolimits_{j=1}^{n-1}P_{j} \right)\ \forall\ n>1 $$
すると$Q_{n} \subset P_{n}$であり、それぞれの$Q_{n}$は互いに素である。したがって$Q_{n}$は**(a)**により正の集合だ。また、以下の式が成立する。
$$ \bigcup \nolimits_{1}^{\infty} P_{j}=\bigcup \nolimits_{1}^{\infty} Q_{j} $$
今、$E$を$\bigcup \nolimits _{1}^\infty P_{n}$の任意の可測な部分集合としよう。
$$ E \in \left( \bigcup \nolimits _{1}^\infty Q_{n} \right)=\left( \bigcup \nolimits _{1}^\infty P_{n} \right) $$
それでは、$\nu (E) \ge 0$を示せば証明は完了する。$E$の定義により、以下の式が成立することがわかる。 $$ E= \bigcup \limits_{j=1}^\infty \left( Q_{j} \cap E \right) $$ それぞれの$Q_{n}$が互いに素であるので、符号測度の可算加法性により、以下が成立する。
$$ \nu (E) = \nu \left(\bigcup \nolimits_{j=1}^\infty \left( Q_{j} \cap E \right) \right) =\sum \limits_{j=1}^\infty \nu \left( Q_{j} \cap E \right) $$
この時、$Q_{n}$が正の集合で、$(Q_{j}\cap E ) \subset Q_{j}$であるため、式の右辺は必ず$0$以上である。
$$ \nu (E) =\sum \limits_{j=1}^\infty \nu \left( Q_{j} \cap E \right) \ge 0 $$
■
Gerald B. Folland, Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications (2nd Edition, 1999), p86 ↩︎