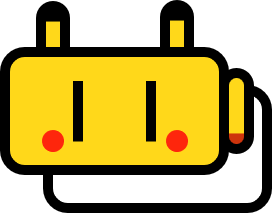リエナール-ヴィーハート電位
概要1
遅延時刻 $t_{r}$で速度 $\mathbf{v}$で動く点電荷 $q$に対するポテンシャルをリエナール‐ヴィーヘルト ポテンシャルLiénard-Wiechert potentials, リエナール‐ヴィヒェルト ポテンシャルと呼び、それぞれ以下のようになる。
$$ \begin{align*} V(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi \epsilon_{0}} \frac{qc}{ (\cR c -\bcR\cdot \mathbf{v})} \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{\mu_{0}}{4 \pi}\frac{qc \mathbf{v} }{(\cR c - \bcR\cdot \mathbf{v} )}=\frac{\mathbf{v}}{c^2}V(\mathbf{r}, t) \end{align*} $$
この時、$\bcR=\mathbf{r} -\mathbf{w}(t_{r})$は遅延位置から観測点までのベクトルであり、$\mathbf{w}(t_{r})$は遅延時刻での点電荷の位置である遅延位置retarded positionである。
説明
1898年、1900年にそれぞれフランスの物理学者リエナールとドイツの物理学者ヴィーヘルトが独立して導出した。
点電荷が動くという状況は、見ているだけで単純そうに見え、ポテンシャルを計算するのが簡単に思えるかもしれないが、実際はそうではない。電荷/電流密度が場所だけで変化する時は、せめて位置が固定されていたが、今はそうではない。遅延時刻に加えて遅延位置も考えなければならない。特に今、遅延時刻は時間に対して定数ではなくなった。これについて詳しく考えなければ、以下のような間違った結果を得ることになる。
$$ \begin{align*} V(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi \epsilon_{0}} \int \frac{ \rho (\mathbf{r}^{\prime},t_{r}) }{\cR} d\tau^{\prime} \\ &= \frac{1}{4\pi \epsilon_{0}} \int \frac{ q\delta \big( \mathbf{r}^{\prime}-\mathbf{w}(t_{r}) \big) }{\cR} d\tau^{\prime} \\ &= \frac{1}{4 \pi \epsilon_{0}}\frac{q}{c} \end{align*} $$
導出
固定位置で変化する電荷/電流密度に対するポテンシャルと電磁場を計算する時を考えよう。動かないので、遅延時刻は時間の変化に無関係で、位置だけに影響を受けた。しかし、今、点電荷が動くと仮定するので、遅延時刻は位置と時間の両方に影響を受ける。したがって、時間に対して定数ではなく変数なので、$t_{r}$ではなく$t^{\prime}$と表記しよう。
$$ V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi \epsilon_{0}} \int \frac{\rho (\mathbf{r}^{\prime},t^{\prime})}{ | \mathbf{r} -\mathbf{r}^{\prime} | }d\tau^{\prime} $$
そして、点電荷は正確に一か所だけに存在するので、電荷密度を以下のように表すことができる。
$$ \rho (\mathbf{r}^{\prime},t)=q \delta \big( \mathbf{r}^{\prime} - \mathbf{w}(t^{\prime}) \big) $$
$\delta$はディラック・デルタ関数である。したがって、ポテンシャルは
$$ \begin{equation} V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi \epsilon_{0}} \int \frac{q \delta \big( \mathbf{r}^{\prime} - \mathbf{w}(t^{\prime}) \big)}{ | \mathbf{r} -\mathbf{r}^{\prime} | }d\tau^{\prime} \end{equation} $$
遅延位置$\mathbf{w}(t^{\prime})$での遅延時刻は、現在の時間$t$から遅延位置から観測点まで来るのにかかる時間を引くと得られる。したがって$\mathbf{w}(t^{\prime})$でのの遅延時刻は
$$ t-\frac{ | \mathbf{r} -\mathbf{w}(t^{\prime}) | }{c} $$
$(1)$で$t^{\prime}$を消去するためにデルタ関数を使う。デルタ関数の定義により$1={\displaystyle \int }\delta \left( t^{\prime}-\big(t-\frac{ | \mathbf{r} -\mathbf{w}(t^{\prime}) | }{c} \big) \right) dt^{\prime}$であるため、掛けても結果には影響がない。したがって
$$ \begin{align*} V(\mathbf{r}, t) &= \frac{q}{4\pi \epsilon_{0}} \int \frac{ \delta \big( \mathbf{r}^{\prime} - \mathbf{w}(t^{\prime}) \big)}{ | \mathbf{r} -\mathbf{r}^{\prime} | }d\tau^{\prime} \int \delta \left( t^{\prime}-t+\frac{ | \mathbf{r} -\mathbf{w}(t^{\prime}) | }{c} \right) dt^{\prime} \\ &= \frac{q}{4\pi \epsilon_{0}} \int \int \frac{ \delta \big( \mathbf{r}^{\prime} - \mathbf{w}(t^{\prime}) \big)}{ | \mathbf{r} -\mathbf{r}^{\prime} | }\delta \left( t^{\prime}-t+\frac{ | \mathbf{r} -\mathbf{w}(t^{\prime}) | }{c} \right) d\tau^{\prime}dt^{\prime} \end{align*} $$
まず、位置に関する積分を解くと、デルタ関数の性質により
$$ V(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi \epsilon_{0}} \int \frac{ 1}{ | \mathbf{r} -\mathbf{w}(t^{\prime}) | }\delta \left( t^{\prime}-t+\frac{ | \mathbf{r} -\mathbf{w}(t^{\prime}) | }{c} \right) dt^{\prime} $$
また、デルタ関数の性質により2
である。この時、$t_{r}$は観測点$\mathbf{r}$にメッセージ(電磁波)を送る粒子が存在した時刻である。つまり、$t$に対する遅延時刻である。動いている'点電荷'について扱っているので、どの時刻$t$でどの位置$\mathbf{r}$に影響を与える点電荷は一つしかなく、したがって遅延時刻も一つだけである。上の式をポテンシャルに代入すると
$$ \begin{align*} V(\mathbf{r}, t) &= \frac{q}{4\pi \epsilon_{0}} \int \frac{ 1}{ | \mathbf{r} -\mathbf{w}(t^{\prime}) | }\dfrac{\delta (t^{\prime}-t_{r}) }{1-\frac{\smallcrH\cdot \mathbf{v}}{c} } dt^{\prime} \\ &= \frac{q}{4\pi \epsilon_{0}} \frac{ 1}{ | \mathbf{r} -\mathbf{w}(t_{r}) | }\dfrac{1}{1-\frac{\smallcrH\cdot \mathbf{v}}{c} } \\ &= \frac{q}{4\pi \epsilon_{0}} \frac{ 1}{ \cR}\dfrac{1}{1-\frac{\smallcrH\cdot \mathbf{v}}{c} } \\ &= \frac{ 1}{ 4\pi \epsilon_{0} }\frac{qc}{(\cR c -\bcR\cdot \mathbf{v} )} \end{align*} $$ ベクトルポテンシャルに対しても同じ論理を適用すると、結果を得ることができる。導出過程はできるだけ詳しく記載するが、説明はほとんど同じなので省略する。電流密度は$\mathbf{J}(\mathbf{r}^{\prime},t^{\prime})=\rho (\mathbf{r}^{\prime}, t^{\prime})\mathbf{v}(t^{\prime})$であるため、
$$ \begin{align*} \mathbf{A} (\mathbf{r}, t) &=\frac{\mu_{0}}{4 \pi} \int \frac{ \mathbf{J}(\mathbf{r}^{\prime},t^{\prime})}{| \mathbf{r} -\mathbf{r}^{\prime}|}d\tau^{\prime} \\ &= \frac{\mu_{0}}{4 \pi} \int \frac{ \rho (\mathbf{r}^{\prime}, t^{\prime})\mathbf{v}(t^{\prime}) }{| \mathbf{r} -\mathbf{r}^{\prime}|}d\tau^{\prime} \\ &= \frac{q\mu_{0}}{4 \pi} \int \frac{ \delta \big( \mathbf{r}^{\prime} - \mathbf{w}(t^{\prime}) \big)\mathbf{v}(t^{\prime}) }{| \mathbf{r} -\mathbf{r}^{\prime}|}d\tau^{\prime} \\ &= \frac{q\mu_{0}}{4 \pi}\int \int \frac{ \delta \big( \mathbf{r}^{\prime} - \mathbf{w}(t^{\prime}) \big)\mathbf{v}(t^{\prime}) }{| \mathbf{r} -\mathbf{r}^{\prime}|} \delta \left( t^{\prime}-t+\frac{ | \mathbf{r} -\mathbf{w}(t^{\prime}) | }{c} \right)d\tau^{\prime} dt^{\prime} \\ &= \frac{q\mu_{0}}{4 \pi}\int \frac{ \mathbf{v}(t^{\prime}) }{| \mathbf{r} -\mathbf{w}(t^{\prime})|} \delta \left( t^{\prime}-t+\frac{ | \mathbf{r} -\mathbf{w}(t^{\prime}) | }{c} \right) dt^{\prime} \\ &= \frac{q\mu_{0}}{4 \pi}\int \frac{ \mathbf{v}(t^{\prime}) }{| \mathbf{r} -\mathbf{w}(t^{\prime})|} \dfrac{\delta (t^{\prime}-t_{r}) }{1-\frac{\smallcrH\cdot \mathbf{v}}{c} } dt^{\prime} \\ &= \frac{q\mu_{0}}{4 \pi} \frac{ \mathbf{v}(t_{r}) }{| \mathbf{r} -\mathbf{w}(t_{r})|} \dfrac{ 1}{1-\frac{\smallcrH\cdot \mathbf{v}}{c} } \\ &= \frac{q\mu_{0}}{4 \pi} \frac{ \mathbf{v}(t_{r}) }{\cR} \dfrac{ 1}{1-\frac{\smallcrH\cdot \mathbf{v}}{c} } \\ &= \frac{\mu_{0}}{4 \pi}\frac{qc \mathbf{v}}{(\cR c -\bcR\cdot \mathbf{v} )} \\ &= \frac{\mu_{0}\epsilon_{0}}{4 \pi\epsilon_{0}}\frac{qc \mathbf{v}}{(\cR c -\bcR\cdot \mathbf{v} )} \\ &= \frac{\mathbf{v} }{c^2} \frac{1}{4 \pi\epsilon_{0}}\frac{qc }{(\cR c -\bcR\cdot \mathbf{v} )} \\ &=\dfrac{\mathbf{v} } {c^2}V(\mathbf{r},t) \end{align*} $$
最後から二番目の等号は$\mu_{0}\epsilon_{0}=\dfrac{1}{c^2}$により成り立つ。
■