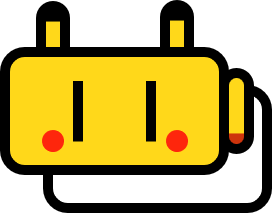積分形式のガウスの法則の応用
説明1
ガウスの法則は、電場を非常に簡単に計算できるが、常にそうとは限らない。ガウスの法則自体は常に成り立つが、数式的な利点は特定の状況でのみ活かせる。以下で説明するように、ガウスの法則を通じて電場を簡単に計算するには、特定の座標系が作る曲面に対して電場$\mathbf{E}$の大きさが一定で、方向が垂直である必要がある。球座標系では、球面に対して大きさが一定で、球面を貫通する方向の電場を簡単に計算できるということだ。電場の大きさが一定の等電場曲面をガウス面Gaussian Surfaceと呼ぶ。ガウス面を描けるケースは3つある。
ガウスの法則
$$ \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_{0}}Q_{\mathrm{in}} $$
球対称

半径が$r>R$の球殻を描く。この球殻がガウス面だ。$d\mathbf{a}$と$\mathbf{E}$の方向が同じなので、二つのベクトルの内積は単純に大きさの積となる。また、球面での電場の大きさは一定なので、定数である。従って、ガウスの法則の公式は以下のように単純化される。
$$ \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \int \left|\mathbf{E} \right| da = \left|\mathbf{E} \right| \int da=\left|\mathbf{E} \right| 4\pi r^2 $$
ガウスの法則により、$\displaystyle \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}=\frac{1} {\epsilon_{0}} Q_\mathrm{in} = \frac{1}{\epsilon_{0}}q$であるから、連立して整理すると次のようになる。
$$ \begin{align*} && \left|\mathbf{E} \right| 4 \pi r^2 &= \frac{1}{\epsilon_{0}}q \\ \implies && \left|\mathbf{E} \right| &= \frac{1}{4\pi \epsilon_{0}}\frac{q}{r^2} \\ \implies && \mathbf{E} &= \frac{1}{4\pi \epsilon_{0}}\frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \end{align*} $$
ここで重要な点は、球の外で電場を測定すると、その結果がまるで全電荷$Q_\mathrm{in}$が球の中心に集まっているかのように出るということだ。つまり、電荷$q$が球内部でどのように分布しているかは重要ではないということだ。
円筒対称

導線を軸として、半径が$s$、長さが$l$の円筒を描く。この円筒がガウス面だ。球対称のときと同じ要領で電場を求めればいい。電荷密度が導線との距離に比例すると仮定しよう。すると、$\rho=ks$($k$は定数)であり、$Q_{\mathrm{in}}$を計算すると次のようになる。
$$ \begin{align*} Q_\mathrm{in}&=\int \rho d\tau \\ &= \int_{0}^l \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^s (ks^{\prime})(s^{\prime}ds^{\prime}d\phi dz) \\ &= \frac{2}{3}k\pi l s^3 \end{align*} $$
電場の積分を計算すると次のようになる。
$$ \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \int \left| \mathbf{E} \right| da = \left| \mathbf{E} \right| \int da = \left|\mathbf{E} \right| 2 \pi s l $$
円筒の表面積が、端の蓋と底が含まれていないことに奇妙に感じるかもしれない。これは、両端で電場の方向と面ベクトルの方向が互いに垂直であるため、磁束が$0$であるからだ。表面積の計算では、電場が垂直に通過する面だけを考慮しなければならない点に注意が必要だ。この2つの式を連立すると$\displaystyle \left| \mathbf{E} \right| 2 \pi s l = \frac{1}{\epsilon_{0}}\frac{2}{3}k\pi l s^3$となり、次の結果を得る。
$$ \mathbf{E} = \frac{1}{3\epsilon_{0}}ks^2 \hat{\mathbf{s}} $$
導線が無限に長い場合に対して計算したが、導線が長く両端から十分に離れた場所であれば、近似値と見なせる。
平面対称

同じ要領で解決する。平板の上下に同じ厚さの直方体を描く。これら2つの直方体がガウス面だ。ガウス面の上面(下面)の面積を$A$としよう。そして、平板の面電荷密度を$\sigma$とすると、ガウス面に囲まれた平板の全電荷量は次のようになる。
$$ Q_\mathrm{in}=\sigma A $$
電場の積分を計算すると次のようになる。
$$ \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}=\left| \mathbf{E} \right| \int d\mathbf{a} = \left| \mathbf{E} \right| 2A $$
従って、ガウスの法則により次が成立する。
$$ \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_{0}}Q_\mathrm{in}=\frac{1}{\epsilon_{0}}\sigma A $$
この時、側面に関する磁束は$0$であるため、上面と下面に関する磁束のみが残り、値が$2A$になる。側面に関する磁束が$0$である理由は、面ベクトル$d\mathbf{a}$と電場$\mathbf{E}$が垂直であるため、内積の値が$0$であるからだ。まとめると下のようになる。
$$ \mathbf{ E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_{0}}\hat{\mathbf{n}} $$
ここで重要な点は、無限平板からどれだけ離れていても、電場の大きさが同じであるということだ。それは、平板から離れるほど、その地点に到達する電場が多くなるからだ。高いところに登れば登るほど、より広く見えるという点を考えればいい。離れていって電場が弱まるが、その分、より多くの場所から影響を受けるため、お互いに相殺されると考えればいい。円筒対称の場合と同じように、平板が広く、角から十分に離れた場所であれば、近似値と見なせる。
結論
電荷を帯びた球が作る電場は$\dfrac{1}{r^2}$に比例し、無限導線が作る電場は$\dfrac{1}{r}$に比例し、無限平板が作る電場は距離に関係なく同じである。
David J. Griffiths, 基礎電磁気学(電磁気学のイントロダクション、金晋昇 訳)(第4版)。2014, p78-82 ↩︎