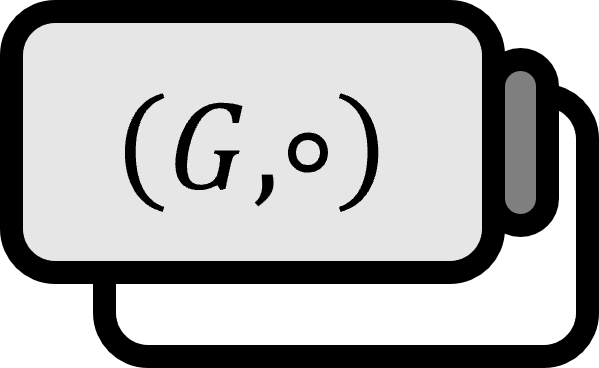抽象代数学における環
定義 1
二つの二項演算、足し算$+$と掛け算$\cdot$に関して以下のルールを満たす集合$R$を環と定義する。
$a$、$b$、$c$が$R$の元の時、
- 足し算に対して交換法則が成り立つ。$$a+b=b+a$$
- 足し算に対して結合法則が成り立つ。$$(a+b)+c=a+(b+c)$$
- 足し算に対する単位元が存在する。$$\forall a \ \exists 0\ \ \mathrm{s.t} \ a+0=a$$
- すべての元の足し算に対する逆元が存在する。$$\forall a \ \exists -a\ \ \mathrm{s.t}\ a+(-a)=0$$
- 掛け算に対して結合法則が成り立つ。$$(ab)c=a(bc)$$
- 足し算と掛け算に対して分配法則が成り立つ。$$a(b+c)=ab+ac\ \mathrm{and} \ (b+c)a=ba+ca$$
説明
要するに、集合$R$が足し算に対して可換群であり、掛け算に対して半群であり、二つの演算に対して分配法則が成り立つ時、$R$を環という。
特に、掛け算に対しても交換法則が成り立つ場合、可換環またはアーベル環と呼ばれる。また、環の定義からわかる通り、掛け算に対する単位元や逆元が存在する必要はない。単位元が存在しても、逆元が存在する必要もない。上記の6つの条件を満たせば、環と言える。
群を扱う時、演算に対する単位元を$e$と表わす。環では演算が二つあるため、どちらの演算に対する単位元か簡単に分かるように異なる記号を使う。足し算に対する単位元は$0$とし、単位元と呼ぶ。掛け算に対する単位元が存在すれば$1$とし、単位と呼ぶ。ある元$a$の掛け算に対する逆元が存在する時、$a$を環$R$の単位と呼ぶ。
群と同じく、環の掛け算に対する単位元も存在するならば、その存在は一意である。各元の逆元も存在すれば、それも一意である。この証明は群で行った方法と同じなので、ここでは書かないが、詳細はこちらを参照。
例
整数の集合$\mathbb{Z}$を考える。上記の6つの条件を満たすため、足し算、掛け算に対する環だ。また、掛け算に対して交換法則も満たすため、可換環だ。単位$1$が存在し、その元は整数の1であり、単位は1と-1だ。(それぞれの逆元として1と-1を持つ)
注意
環では、掛け算に対する単位元や逆元が存在する「必要」がない。だから、群でのように安易に消去することができない。つまり、$a,\ b,\ c$が環$R$の元の時、$ab=ac$として$b=c$と結論づけることはできないのだ。$a$の逆元が必ず存在するわけではないからだ。
同様に、$a^2=a$としても、安易に$a=0$や$a=1$という結論を出すことはできない。環を扱う際には、この点に注意しよう。
Fraleigh. (2003). 「抽象代数入門(第7版)」: p167. ↩︎