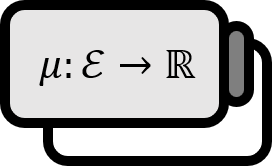ルベーグ積分
ビルドアップ
リーマン積分の一般化を考える前に、単純関数simple functionというものを定義する必要がある。
関数値が非負で、$\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ の値域が有限集合 $\left\{ a_{1} , a_{2}, \cdots , a_{n} \right\}$ であるとし、$A_{i} = \phi^{-1} \left( \left\{ a_{i} \right\} \right) \in \mathcal{M}$ を満たすとき、$\phi$ を単純関数と呼ぶ。単純関数は次の性質を持つ。
- (i): $i \ne j$ なら$A_{i } \cap A_{j} = \emptyset$
- (ii): $\displaystyle \bigsqcup_{k=1}^{n} A_{k} = \mathbb{R}$
- (iii): $\displaystyle \phi (x) = \sum_{k=1}^{n} a_{k} \mathbb{1}_{A_{k}}(x)$ は測度可能関数である。
ここで、$\mathbb{1}_{A}$ は指示関数である。
単純関数は、その定義より扱いやすい3つの要素で構成されている。第一に、関数値が非負であるため符号を考える必要がなく、第二に有限であるため自由に足し引きができ、第三に測度可能である。数学の様々な分野で単純simpleという言葉は多様に使われるが、少なくとも実解析においては「複雑」の反対と考えてよい。これだけ扱いやすく便利な単純関数を定義すると、すぐにリーマン積分をカバーする新しい積分を考えることができる。
定義と基本性質
単純関数のルベーグ積分
$\phi$ が単純関数で $E \in \mathcal{M}$ としたとき、次を単純関数 $\phi$ のルベーグ積分という。
$$ \int_{E} \phi dm := \sum_{k=1}^{n} a_{k} m (A_{k} \cap E) $$
単純関数のルベーグ積分は次の性質を持つ。
- [1]: 全ての $a>0$ に対して $\displaystyle \int_{E} a \phi dm = a \int_{E} \phi dm $
- [2]: 二つの単純関数 $\phi , \psi$ に対して $\phi \le \psi$ なら $\displaystyle \int_{E} \phi dm \le \int_{E} \psi dm$
- [3]: $A, B \in \mathcal{M}$ に対して $A \cap B = \emptyset$ なら $\displaystyle \int_{A \cup B} \phi dm = \int_{A} \phi dm + \int_{B} \phi dm$
ここで、$m$ はルベーグ測度である。単純関数という条件は非常に強力で特殊であるため、様々な場面で使うことができない。これに区分求積法のアイデアを加えると、ある程度満足のいく「ルベーグ積分」が完成する。
測度可能関数のルベーグ積分 1
$\phi$ が単純関数であるとき、関数値が非負な測度可能関数 $f$ と $E \in \mathcal{M}$ に対して、次を測度可能関数 $f$ のルベーグ積分lebesgue Integralという。 $$\int_{E} f dm := \sup \left\{ \left. \int_{E} \phi dm \ \right| \ 0 \le \phi \le f \right\}$$
測度可能関数のルベーグ積分は次の性質を持つ。
- [1]': 全ての $r \ge 0$ に対して $\displaystyle \int_{E} r f dm = r \int_{E} f dm$
- [2]': 二つの測度可能関数 $f, g$ に対して $f \le g$ なら $\displaystyle \int_{E} f dm \le \int_{E} g dm$
- [3]': $A, B \in \mathcal{M}$ に対して $A \cap B = \emptyset$ なら $\displaystyle \int_{A \cup B} f dm = \int_{A} f dm + \int_{B} f dm$
- [4]': $A, B \in \mathcal{M}$ に対して $A \subset B$ なら $\displaystyle \int_{A} f dm \le \int_{B} f dm$
- [5]': $N \in \mathcal{N}$ なら $\displaystyle \int_{N} f dm = 0$
- [6]': $\displaystyle m(E) \inf_{E} f \le \int_{E} f dm \le m(E) \sup_{E} f$
これらの基本性質の他に、次のように広く使われる定理を紹介する。
定理
測度空間 $( X , \mathcal{E} )$ の測度可能関数 $f \ge 0$ と全ての測度可能集合 $A \in \mathcal{E}$ に対して $$ \int_{A} f dm = 0 \iff f = 0 \text{ a.e.} $$ ここで、$\text{a.e.}$ はほぼ至る所を意味する。
証明
$( \implies )$
$E := f^{-1} ( 0 , \infty)$ に対して $m(E) = 0$ なら $f$ はほぼ至る所 $f=0$ である。証明のために $\displaystyle E_{n} := f^{-1} \left[ {{1} \over {n}} , \infty \right)$ とおくと $\displaystyle E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_{n}$ であり、$\displaystyle \lim_{n \to \infty} E_{n} = E$ が成り立つ。ここで単純関数 $\displaystyle \phi_{n} := {{1}\over {n}} \mathbb{1}_{E_{n}} \le f$ を考えると $$ {{1}\over {n}} m( E_{n} ) = \int_{A} \phi_{n} dm \le \int_{A} f dm = 0 $$ ゆえに $$ {{1} \over {n}} m(E_{n}) \le 0 $$ すなわち、全ての $n \in \mathbb{N}$ に対して $m(E_{n}) = 0$ である。
一方、$E_{n} \subset E_{n+1}$ であるため次が成り立つ。 $$ m \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_{n} \right) = \lim_{n \to \infty} m (E_{n}) = m(E) = 0 $$
$( \impliedby )$
$f$ がほぼ至る所 $f=0$ であり、単純関数 $\phi$ が $0 \le \phi \le f$ を満たすため、$\phi$ もまたほぼ至る所 $\phi = 0$ である。したがって $\displaystyle \int_{A} f dm = 0$ である。
■
Capinski. (1999). Measure, Integral and Probability: p77. ↩︎