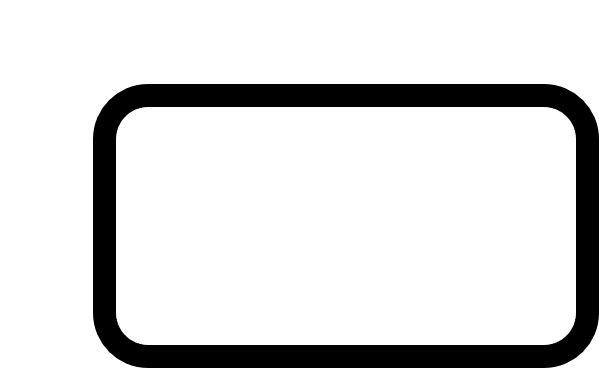数学で「よく定義された」という表現
用語
数学において よく定義されているwell-definedという表現は、対象を曖昧さなく客観的かつ明確に認識できるときに用いる。
説明
よく定義された関数
“よく定義されている"という表現は主に関数に対して用いる。集合 $X$ と $Y$ に対して、$X$ から $Y$ への関数とは、各 $X$ の元にただ一つの $Y$ の元を対応させる関係を意味する。すなわち よく定義された関数well-defined functionとは次の二条件を満たすことを指す。
- 定義域 $X$ のすべての元 $x$ に対して、像 $f(x)$ が存在する。
- $x_{1} \sim x_{2}$ ならば $f(x_{1}) = f(x_{2})$ である。
ここで $\sim$ は 同値関係である。すなわち同一の対象を異なる表現で表した場合でも対応する像が等しくなければならないという意味である。それぞれの条件が破られる例を具体的に見てみる。
- $X = [0, 1]$、$Y = \mathbb{R}$ に対して、$f : X \to Y$ を $f(x) = \dfrac{1}{x}$ とすると、$f(0)$ の値が存在しないので、$f$ はよく定義された関数ではない。
- $X = \mathbb{Q}$、$Y = \mathbb{R}$ に対して、$f : X \to Y$ を $f(\frac{a}{b}) = a$ のように定めると、$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ であるが、それぞれに対応する像は等しくない。 $$ f(\textstyle \frac{1}{2}) = 1 \ne 3 = f(\frac{3}{6}) $$ したがってこのような $f$ はよく定義された関数ではない。
よく定義された演算
結合法則を満たさない 二項演算 を用いて三項式を作ると、その演算はよく定義されない。例えば加法や乗法は結合法則が成り立つため、以下のように書いたとき、第一の計算か第二の計算のどちらを先にしても答は変わらない。
$$ 1 + 2 + 3 = 6, \qquad 2 \times 3 \times 4 = 24 $$
しかし除法の場合は以下の例のように、どちらの演算を先に行うかによって答が変わる。
$$ \frac{1}{8} \overset{?}{=} 1 \div 2 \div 4 \overset{?}{=} 2 $$
したがって上式はよく定義されておらず、意図を明確に示すために括弧を用いるか乗算記号のみを使うのが望ましい。
$$ \frac{1}{8} = (1 \div 2) \div 4, \qquad 1 \div (2 \div 4) = 2 $$
有名な釣り問題である $48 \div 2(9 + 3) = ?$ のような場合も、よく定義されていない問題と見なせるので、答えが何かを議論するのは時間の無駄だ。括弧をきちんと付けて先へ進もう。