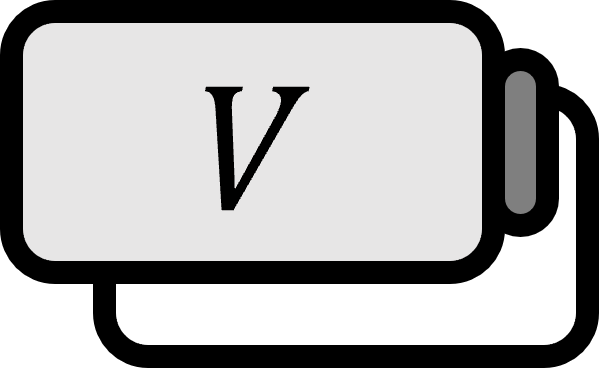線形代数学における剰余類と商空間
定義1
$V$を $F$-ベクトル空間、$W \le V$を 部分空間とする。$v \in V$に対して、次の集合
$$ \left\{ v \right\} + W := \left\{ v + w : w \in W \right\} $$
を $v$を含む $W$の 剰余類coset of $W$ containing $v$という。左辺の $+$ は 集合の和である。
説明
しばしば $\left\{ v \right\} + W$ の代わりに $v + W$ と略記する。
$W$のすべての剰余類の集合を $\left\{ v + W : v \in V \right\}$ とする。加法と ($F$ による)スカラー倍を次のように定義する。
$$ (v_{1} + W) + (v_{2} + W) = (v_{1} + v_{2}) + W,\quad \forall v_{1}, v_{2} \in V $$
$$ a(v + W) = av + W\quad \forall v \in V \text{ and } a \in F $$
するとこの集合は再び $F$-ベクトル空間になる。このベクトル空間を $V/W$ と記し、$W$で割った $V$の 商空間quotient space of $V$ modulo $W$と呼ぶ。ここまで定義を受け入れても、このようなベクトル空間をわざわざ 商空間 と呼び、割り算と同様に $V / W$ と表記する理由を一度に察するのは容易ではない。詳しい説明とともに理解しよう。全空間と部分空間を次のように置く。
$$ V = \mathbb{R}^{5} = \left\{ (a,b,c,d,e) \right\} $$
$$ W = \mathbb{R}^{2} = \left\{ (a,b,0,0,0) \right\} $$
すると商空間を 生成する基底は以下の通りであることが分かる。
$$ \left\{ (0,0,1,0,0) + W, (0,0,0,1,0) + W, (0,0,0,0,1) + W \right\} $$
すなわち $V/W = \left\{ v + W : v \in V \right\}$ は3次元ベクトル空間である。
$$ V / W \cong \mathbb{R}^{3} $$
以下のように書くと、商空間の表記法がまるで指数法則で次元を下げるかのように適切であることが一目で分かる。
$$ V/W = \dfrac{V}{W} = \dfrac{\mathbb{R}^{5}}{\mathbb{R}^{2}} = \mathbb{R}^{5-2} = \mathbb{R}^{3} $$
実際に 次の式が成り立つ。
$$ \dim(V/W) = \dim(V) - \dim(W) $$
命題
(a) $v + W$が $V$の部分空間であることは $v \in W$であることと同値である。 (代数学での証明)
(b) $v_{1}, v_{2} \in V$に関して、$v_{1} + W = v_{2} + W$であることは $v_{1} - v_{2} \in W$であることと同値である。 (代数学での証明)
(c) $V/W$はベクトル空間であり、零ベクトルは $0_{V} + W = W$である。 ($0_{V}$は $V$の零ベクトルである。)
証明
(a)
$(\Longrightarrow)$
$v + W$が $V$の部分空間であると仮定する。すると、$0_{V}$を $V$の零ベクトルとすると、$0_{V} \in v + W$である。したがってある $w \in W$に対して $0_{V} = v + w$であり、$w = -v \in W$である。$W$は $V$の部分空間であるからスカラー倍に関して閉じており $v = -(-v) \in W$である。
$(\Longleftarrow)$
$v \in W$と仮定する。$v + W$が $V$の部分空間であることを示すには 加法とスカラー倍に関して閉じていることを示せばよい。 $v + w_{1}, v + w_{2} \in v + W$とする。これら二つを足すと次のとおりである。
$$ (v + w_{1}) + (v_{1} + w_{2}) = v + (v + w_{1} + w_{2}) $$
$W$は部分空間だから加法に関して閉じており、仮定により $v$は $W$の元であるから、ある $w_{3} \in W$に対して次が成り立つ。
$$ v + (v + w_{1} + w_{2}) = v + w_{3} \in W $$
次に $a \in F$とする。すると同様に仮定より、ある $w_{4} \in W$に対して次が成り立つ。
$$ a(v + w) = v + \left( (a-1)v + aw \right) = v + w_{4} \in W $$
■
(b)
$(\Longrightarrow)$
$v_{1} + W = v_{2} + W$と仮定する。すると $V$の零ベクトル $0_{V}$とある $w \in W$に対して次が成り立つ。
$$ v_{1} + 0_{V} = v_{2} + w \implies v_{1} - v_{2} = w \in W $$
$(\Longleftarrow)$
$v_{1} - v_{2} \in W$と仮定する。すると
$$ \begin{align*} v_{2} + W &= \left\{ v_{2} + w : w \in W \right\} \\ &= \left\{ v_{2} + \left( (v_{1} - v_{2}) + w \right) : w \in W \right\} \\ &= \left\{ v_{1} + w : w \in W \right\} \\ &= v_{1} + W \end{align*} $$
■
関連項目
Stephen H. Friedberg, Linear Algebra (4th Edition, 2002), p23 ↩︎