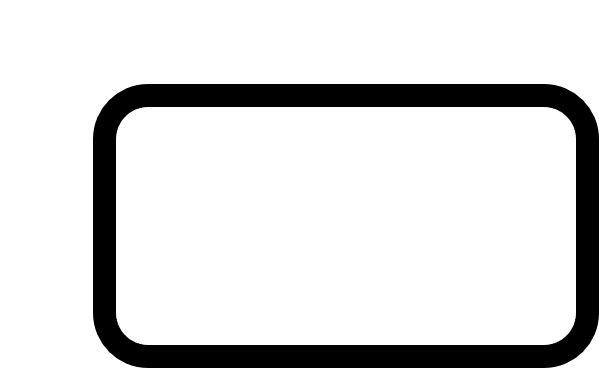数学において一般性を失わないという表現
用語 1
“一般性を失わずにWithout Loss of Generality, WLOG $P$ を仮定する"という表現は主に数学的な証明で「具体的には $P$ を仮定しても全体の議論には影響しない」という意味で用いられる。
例
簡単な例
極めて簡単な例として、「二つの実数 $x, y$ について $xy = 0$ ならば $x = 0$ あるいは $y = 0$ である」という命題を証明すると考えてみる。これはあくまで WLOG がなぜ必要でどう使われるかを理解するための例なので、可能な限り省略せずに説明する。
$x$ と $y$ はそれぞれ $0$ か $0$ ではないかの二通りがあり、全場合の数はその積である $4$ 通りである。すべての場合を見ていこう。
Case 1. $x = y = 0$
この場合 $x$ と $y$ はともに $0$ である。
Case 2. $x = 0, y \ne 0$
この場合 $x$ が $0$ である。
Case 3. $x \ne 0, y = 0$
この場合 $y$ が $0$ である。
Case 4. $x \ne 0, y \ne 0$
$xy = 0$ の両辺を $xy$ で割ると $1 = 0$ となる。これは $x \ne 0, y \ne 0$ という場合に問題があることを意味するので、この場合は除外しなければならない。
結論として、$xy = 0$ ならば $x = 0$ あるいは $y = 0$ でなければならない。
■
この短い証明では本能的に Case 2 と Case 3 が実は同じ条件であると感じられる。$x$ も $y$ も同じ実数であり乗法の順序が重要でない状況において、単に文字を変えて書いたという理由でこれらのケースを別々に分けるのは無意味である。このとき「一般性を失わずに $x = 0$, $y \ne 0$ と仮定する」と言えば、それはそのときの論理を $x$ と $y$ を入れ替えて適用すれば済むという意味になる。
- まだ数学に慣れておらず「一般性を失わずに」という言葉がどういう意味か気になる人に情報を伝えるという目的上、背理法や体の公理により $x$ と $y$ が両方とも $0$ でないため乗法の逆元云々という話はすべて省略した。
よく見る例
教科書でより簡単に見られる例として次のようなものが挙げられる。
- 一般性を失わずに、 $A$ が 上三角行列 であると仮定する:以後の証明は $A$ が下三角行列でも同じであるという意味である。
- 一般性を失わずに、三角形の三辺の長さが $a \le b \le c$ であると仮定する:以後の証明は $a, b, c$ の順序を入れ替えても同じであるという意味だ。
- 一般性を失わずに、 $\left\| \mathbf{v} \right\| = 1$ と仮定する:証明の便宜上ベクトルの大きさを $1$ と置き、もし大きさが $1$ でなくても $\mathbf{u} = \mathbf{v} / \left\| \mathbf{v} \right\|$ のように分ければ問題ないという意味である。
Harrison, J. (2009). Without Loss of Generality. In: Berghofer, S., Nipkow, T., Urban, C., Wenzel, M. (eds) Theorem Proving in Higher Order Logics. TPHOLs 2009. Lecture Notes in Computer Science, vol 5674. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03359-9_3 ↩︎