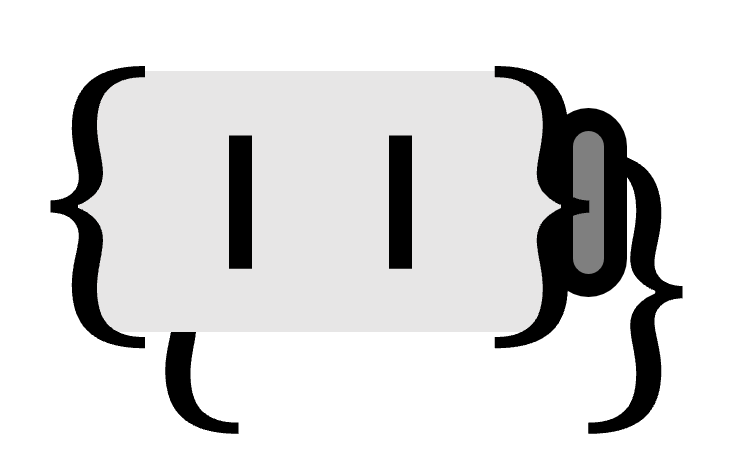可算集合と不可算集合
定義 1
説明
可算集合という概念は、韓国人を含む東洋人にとって受け入れやすいわけではない。これは英語を含むインド・ヨーロッパ語族の思考方法と私たちのマインドが根本的に異なることによる。あるのは、ヨーロッパの言語は名詞に性があり、数や格に応じて動詞と形容詞が変化するなど、「共感しにくい」文法特性を持つことが多い。特にこの数については、文法に触れる前に、そもそもなぜ区分されるのか理解しにくいものが多いが、実はこの言語的思考方法の違いが東西の数学の違いとして表れる。
可算、つまり「一つ、二つ、…」と「いくつ」か数えることができる対象を言う。例えば人間や腕時計、オレンジなどがそうだ。数えられないものとしては、水やパンのように数ではなく量があり、任意に分割できるものを言う。だから A dogは犬一匹で、Dogsは複数の犬だが、Dogは犬肉を意味することになる。もちろん言葉には文脈があり、これほど極端に解釈はされないが、可能であるという話だ。
この違いをなぜ区別するかを理解させるよりも、私たちも変なものを使っていると説明する方がよかった。例えば、韓国を含む東アジア国家は「単位」というまったく役に立たなさそうな言葉を使う。例えば人は人、動物は匹、長く細いものは本、薄く広いものは枚、建物は棟などだ。韓国語は必ずこのように使い、英語ではこれらの表現を全く使わないという意味ではなく、思考の基底でこれを自然に受け入れているという点が重要だ。
つまり、鉛筆を数えるとき「鉛筆一本」と単に言うこともできるけど、「鉛筆一本貸して」と言ったとき、なぜ鉛筆を本で数えるのか変だと感じない「感覚」が実際の言語習慣を決定づける。一方で、英語を骨まで受け入れないと、コミュニケーションに問題がないほど英語を上手に話せても、a, theなどの冠詞の使い方がめっちゃくちゃで、どこかおかしくならざるを得ない。言語って本来こんなものだ。受け入れればいいし、受け入れざるを得ない。そして言語間の違いは、元々使っていたものだから、そういうものだと思ってスルーしても実は全く問題ない。
- [1]:$X \sim \mathbb{Z}$ ならば、$X$ は可算集合だ。
- [2]:$X \sim \mathbb{Q}$ ならば、$X$ は可算集合だ。
- [3]:$X \sim \mathbb{R}$ ならば、$X$ は非可算集合だ。
しかし驚くべきことに、こうした違いは実際の数学でも現れ、[3]のように具体的に非可算集合を提案できる。この事実は集合論の父、ゲオルク・カントールによって証明され、彼自身もそうした非可算集合の存在に驚いたという。しかし、可算と非可算を抜きにしても、東アジアの数学ではこれらの概念が思い浮かぶことがあったのだろうか?不可能だと断言はできないが、ピタゴラス以後、非可算集合を発見するまでにかかった時間はなんと約2500年である。東洋で純粋数学が発展していたら、東洋独自の視点で驚くべき成果を見つけ出していたかもしれないが、可算と非可算の概念は間違いなくインド・ヨーロッパ言語族が残した遺産だ。
証明
おそらくカントールは、すべての無限集合が可算集合であることを証明しようとしたのかもしれない。直感的にもその方が簡単で、本当であればすべての集合を自然数に引き下げて考えることができるからだ。カントールの旅を追って、まず[1]と[2]の証明を見てみよう。
[1]
$\mathbb{N}$ と $\mathbb{Z}$ の間に全単射が存在することを示せばよい。次のような対応関係を定義すると全単射となる。 $$ (1,2,3,4,5, \cdots ) \mapsto (0,-1,1,-2,2, \cdots ) $$
■
[2]
$\mathbb{N}$ と $\mathbb{Q}$ の間に全単射が存在することを示せばよい。次のような対応関係を定義してみよう。 $$ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & 7 & \cdots \\ 3 & 5 & 8 & \ddots & \\ 4 & 9 & \ddots & & \\ 10 & \ddots & & \\ \vdots & & \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1/1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 & \cdots \\ 2/1 & 2/2 & 2/3 & \ddots & \\ 4/1 & 4/2 & \ddots & & \\ 5/1 & \ddots & & \\ \vdots & & \end{bmatrix} $$ ここで約分を行なった後、重複する要素とそうでない要素が生じる。例えば、$2/2 = 1/1$ より重複である。これから、このような要素を重複しない要素に順番に$-1$ を掛けた要素に対応させてみよう。 $$ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & 7 & \cdots \\ 3 & 5 & 8 & \ddots & \\ 4 & 9 & \ddots & \\ 10 & \ddots & \\ \vdots & & \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1/1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 & \cdots \\ 2/1 & -(1/1) & 2/3 & \ddots & \\ 4/1 & -(1/2) & \ddots & & \\ 5/1 & \ddots & & \\ \vdots & & \end{bmatrix} $$ すると、この対応は全単射となる。
■
[3]
中学校から数を学ぶときは、自然数、整数、有理数、実数、複素数の順で学ぶが、ここまで証明したカントールがやろうとしたのは明白である。つまり、$\mathbb{N} \sim \mathbb{R}$ であることを示す全単射を見つけようということだ。しかし、推測するにその試みは次々に失敗し、結局そのような全単射が存在しないことを証明しようとしたのだろう。このとき使用した方法が、その有名なカントールの対角線論法である。
李興天 訳、林游鳳. (2011). 集合論(Set Theory: An Intuitive Approach): p219. ↩︎