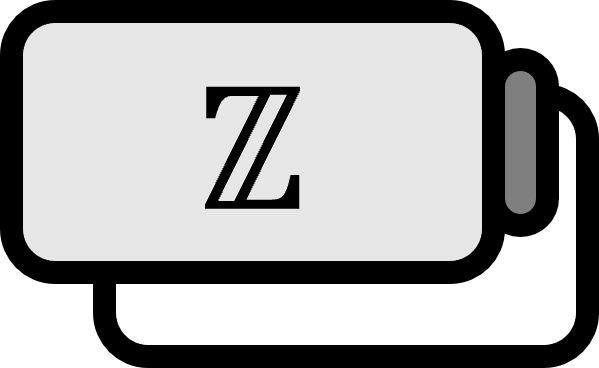ガウス整数
定義 1
$\mathbb{Z} [i] := \left\{ a + i b : a, b \in \mathbb{Z} \right\}$をガウス環と言い、その要素をガウス整数という。
定理
- [1]: $\overline{i} = i^{3}$
- [2]: $( a \pm ib ) + ( c \pm id) = (a \pm c) + i (b \pm d)$
- [3]: $( a + ib )( c + id) = (ac - bd) + i (ad + bc)$
説明
$i$は二次方程式$x^2 +1 = 0$の複素根であり、$\mathbb{Z} [i]$は整数環$\mathbb{Z}$の拡張である。実数体$\mathbb{R}$が複素数体$\mathbb{C} = \mathbb{R} [i]$に拡張されるのに似ていて、その理由も大差ない。整数を議論する上で無理数でさえもタブーではないのだから、複素数を考えない理由はない。むしろ、無理数よりも簡単だ。
整数に素数があるように、ガウス整数にもガウス素数がある。 $\mathbb{Z} [i]$上では次のように通常の数式展開が可能である: $$ \begin{align*} (7 + i2)(4 -i 2) =& (28 + 4) + i (- 14 +8 ) \\ =& 32 - i 6 \end{align*} $$ また、ある自然数$n \in \mathbb{N}$が与えられたとき、有限環$\mathbb{Z}_{n}$に対しても$\mathbb{Z}_{n}[i]$を考えることができる。例えば、$n = 7$とすると、上記の展開は次のように変わる: $$ \begin{align*} (7 + i2)(4 -i 2) =& (28 + 4) + i (- 14 + 8 ) \\ =& 32 - i 6 \\ & \equiv 4 - i 6 \pmod{7} \\ & \equiv 4 + i \pmod{7} \end{align*} $$ 自然に合同式を使用したことに注目。$\mathbb{Z}$を$\mathbb{Z} [i]$に一般化したいという欲求は、数学者にとって言葉で説明するのも難しいほど自然なものだ。解析学が$i$を許容したことによる革新と比べられるかはわからないが、整数論もまた豊かで美しくなったことは確かだ。ただちに代数学の基本定理を考えても、$\mathbb{Z} [i]$에서は$d$次の合同方程式が$d$個の解を持つといった汚い話はない。複素数が導入されたことにより、ただきれいに正確に$d$個の解を持つと言えるようになったのだ。
ここから一歩進んだ整数体系としては、アイゼンシュタイン整数がある。
証明
[1]
$i$の定義と共役の性質により $$ \overline{i} = -i = i^{3} $$
■
[2]
$\mathbb{Z} [i]$は環であり、加算に対し結合法則と交換法則が成り立つので $$ \begin{align*} ( a \pm ib ) + ( c \pm id) =& a \pm ib + c \pm id \\ =& a \pm c + ib \pm id \\ =& (a \pm c) + i (b \pm d) \end{align*} $$
■
[3]
[2]に基づき $$ \begin{align*} ( a + ib )( c + id) =& ac + ibc + iad + (- 1)bd \\ =& (ac - bd) + i (ad + bc) \end{align*} $$
■
Silverman. (2012). 数論へのフレンドリーな導入 (第4版): p267。 ↩︎